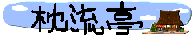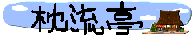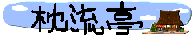
『錯綜』89−92
ホームへもどる
自作詩集へもどる
目 次
巻頭言
ビードロの街
ガラス越しの飛翔
寸劇
旋律
霧瘴
退屈は嫌い
旅路
宝玉
遥かなるアタラクシア
青磁の猫
従順な羊
なみだ
喪失の“Δ”
秋雨は愁雨となりて
意志世界の終焉
Blue year’s sonnet
ケロイドの朝
哀願
猫又の嘆き
夜光虫
BIRTH
Tear
閉ざされた教室
“錯綜”巻頭言
この反古にも似た幼稚で退嬰的な言質の集積は、おそらくこれを読む全ての人を退屈させるだろうが、ひとりの少年の想像と矛盾と屈折とを内包する錯綜の自己完結的な表現の数々に幾人かの耳目を幾分かとどめることがあるとすれば光栄である…。
1992年11月
青春とは徒労の季節である。
その季節は
少年が世界の意義性を疑う
その日からはじまる。
目次にもどる
ビードロの街
ビードロで造られた街に
蟻たちが歩き回り
文明と秩序を誇っていた
彼は突然やってきた
ビードロの建造物は崩れ
ガレキが法則に従って
無情に降りそそぎ
蟻たちを押し潰した
彼が発した熱は
ビードロを溶かし尽くして
再び冷え固まり
女神の像を造りあげる
蟻たちの体液が滲み
血肉の混じりあった
朱色の美
ミッシェルの預言の呪い
街は吹雪の中
ガレキも像も白銀の中
大地は全て雪と氷の中
空には重い雲が垂れて
混沌から天地が創造された後の
夜の静寂
久遠の刻を経て
新たな蟻たちが
ビードロの廃墟を発見して
彼らは想うことだろう
地獄の惨劇を
目次にもどる
ガラス越しの飛翔
僕は雨の中空を飛んだ。
僕の肉体は椅子に縛られて
ガラス越しに僕を見ていた。
街は降りしきる雨のために霞んだ。
雨は僕の翼を重くはしなかったが
空が僕の肩に重くのしかかっていた。
flying … in the sky.
僕は雨の中空を飛んでいたが
歓びは湧かなくなっていた。
僕は振り返った。
雨に霞む視線が冷たく感じた。
僕は空を背に飛び立って
僕の肉体へと帰っていった。
再び椅子に縛られた僕は
ガラス越しの景色を見ていた。
目次にもどる
寸劇
巨塔の狭間に吹く風
腐敗・堕落という
the moment
t 生命が一瞬に蒸発する
G 無機の下僕たちを伴って
Z 文明が一瞬に崩壊する
D 有機の主人たちに殉じて
W
H 塔は神の手によって壊される
h 文明は波斯に滅ぼされる
O
O 彼らは堕ちていく
∞ 限りなく空虚な世界へ
O 享楽への執着は消えて
R 躰は軽くなっていく
N 限りなく堕ちていく
街は廃墟になり
砂に埋もれていく
ただ残るのは砂の空漠
造られた砂の城は
風に削られていき
ただ残るのは砂の広漠
目次にもどる
旋律
時空が歪むほどの巨大な質量
それに押し潰されそうな僕
骨髄が軋み臓腑が悲鳴をあげる
芸術も哲学も僕を救けないし
僕はそれらを解してもいない
ただ聞こえるのは古い時計の響き
その針は滅亡への時と血肉を刻む
アヴェ・マリアは葬送曲と変わる
地上には荒廃の風が吹きぬけ
僕は静かに考えている
再生への可能性と
来ないであろう救済と
あまりの希薄と空虚について
滅びの瞬間は陶酔のうちに
胸にはなにかが詰まっているが
僕にはそれを吐き出せはしない
それは僕の内面に拡がって
亡者たちの内面と共鳴していく
地上に美しい旋律が流れる
約束の福音
地上に哀歌が鎮魂歌が流れる
目次にもどる
霧瘴
廃墟に霧がかかっていた
それは酸の霧であった
霧は僕の視界を遮っていた
霧は僕らを蝕み
廃墟を瓦礫を溶かした
全ては砂に還っていく
僕らは土に還れはしない
霧は惨劇を隠す
僕の眼にはただ紫が映り
一瞬それが紅に変わって
混沌へと堕ちていった
滅びには美は見えない
僕は身に迫る醜悪を感じた
雲は重く垂れ下がる
全ては砂に還っていく
霧はその砂を少し湿らせる
目次にもどる
退屈は嫌い
曇天が此方に錨をおろし
愁雨しんしんとしんしんと
木々もざわめきを消し去り
形而上の風景に苛立つ僕の心
目次にもどる
旅路
一歩、一歩、次の一歩を探し求める
無数の軌跡を旅路というか?
目次にもどる
宝玉
流血の荒野に戦士独り
夜露置く草枕あらず
月光は真紅の飛礫を照らし
双眸に宝玉、夜露にひかり
目次にもどる
遥かなるアタラクシア
空を見上げると、赤闇、蒼闇、曇天の夜空
地上を見渡すと、暗灰の営為、煌めくネオン
滅びへと疾走していく怪物の車たち
モータリゼーションもエボリューションもただ
僕らを芯まで疲労させる反存在さ
僕らが欲しいのは深き森林の安楽椅子なのに
目次にもどる
青磁の猫
明らかな青磁の煌めきに
僕は一匹の雌猫を発見した
“飼われているのかは知らない
捕らわれているに違いない”
彼女は人間の酔狂を呪った
二者は阿を異にして
吽をともにせねばならぬ
“人間が葦に過ぎないとしたら
彼らが造った自らを滅ぼす蒸気
その一滴は癒しがたく彼らを蝕む
その時吾が眷属も−然り−
吾らは人間の罪業の‘報い’に焼かれよう”
彼女は人間の狂態を嗤った
最後の瞬間
僕は自らを“蒸発”するに任せていた
青磁の猫は姿を変じながら
僕の最期の眼眸を凝えていた
−断章三四七変調
パスカル「パンセ」より−
目次にもどる
従順な羊
動物愛護者たちが微笑う
牧場に数匹の犬と数十匹の牧羊たち
高級な食事、与えられた流行、快適な生活空間
刺激的な音楽、恋愛遊戯、エトセトラ
羊たちは自分らの至福を疑わない
疑わない、惑わない、逡巡しない
“コギト・エルゴ・スム”
思索家の造語もどこかむなしい
彼らの存在を稀釈する道化者
動物愛護をかたる者たちが微笑う
“君たちの幸福は約束されている”
アウシュビッツ、チクロンB、人間石鹸
悲嘆を背負い続ける人々の永遠の罪業
従順な羊たちの末路
目次にもどる
なみだ
I
悲しくて涙は出ない
寂しくて寂しくて孤独
一縷の涙が頬を這うのは
ひとがひとりである証明
II
人が解り合えるなら
錯覚と誤解
虚像と実像の一側面
それらの連綿とした泥の中に
赤い糸をたぐり出す仕事を
誤るはずもなかろうに
五感の無為な所作に
愚かしい歴史が
螺旋のように連なる
誰も虚無の螺旋を巻き直せない
人は真に解り合えぬ
悲しいとはそれが悲しい
寂しくて弱い人間に泣く
III
血縷の朱の泪に僕の躯は蒼く染まる
僕の蒼き躯に朱き血縷の泪が流れる
IV
彫像の煌めく涙に
あまりに冷淡な
蠢く歴史の悲嘆に
あまりに冷淡な
憎悪しようか
哭する人間を
V
嬰児は孤独であることを覚えて
夜の醒間(静閑)の中をただよい
すすり泣く自分を冷めた眼で見つめる
幾人かの嬰児らの存在に気づく
ニル・アドミラリな眼、眼、眼
強いのか弱いのか
VI
ひとときくるくるしてる
けったいにふさがった僕を
壁の中から
不思議と目腫らした少女が
連れ去っていった
VII
蒼き赤子の肌が腐蝕する
生命なき人形の死屍
蒼さが凍りつく、蒼さがひび割れる
傷口が叫び!赤子はあかき涙を流す
目次にもどる
喪失の“Δ”
小さい頃から社会の喧噪が嫌いだった
人の体臭と傲慢な歩みの迹を避けたかった
御為ごかしな親たちは僕を学校に連行して
傷だらけの教室に座らせて安心を買った
扇動者たちは“Δ”、唱和することを求めた
生徒たちは“Δ”、従順に唱和した
僕はひとり黙っていた、心の中で“Δ”
…………………………………
“Δ”は僕に非人間の烙印を押した
炸裂する衝音、喧噪の悲鳴
その中に消えた
“Δ”を拒否する一個の僕
目次にもどる
秋雨は愁雨となりて
曇天は夜の帳に覆われ
閉じた眼で雨音を聞く
軽快な音楽は止んで
僕の心の静寂
蟻の巣穴を雨垂れが犯して
住み人は眠れぬ夜を過ごす
幻想の廃墟
雨音が反響する境界の
秋雨は愁雨となりて
僕の夜を犯す黒い雨音
ひとはが落ちて描く同心円
しづかにしづかに
愁雨止んで
帳が陽に破れかけた
潅木のひとはが
虚空を愛撫する一刻
目次にもどる
意志世界の終焉
白くかなしい骨皮の森林が静かに
地平に沈み込む−静穏か無か−
石灰質の砂が乾き さらさらと流れ
塵芥は微風に巻き上げられず
限りなく平坦に進む宇宙の膨張に
ネゲントロピーの挽歌は奏でられず
羊水は蒸発し−限りなく開放された−
静穏か無かは知れぬ終焉の絵画
世界の本質は盲目的な生への意志である
ショーペンハウエル
目次にもどる
Blue year’s sonnet
頚、肩、背の各所が痛む
快い疲労が僕を投げ寝かせたのだ
蛍光の部屋は薄緑に茫として
ヒュプノスの誘惑に眼がぐるぐるする
感傷はこれほどに人を疲れさすのか
解煩の鐘の音が内耳をそっとくすぐる
惰性と倦怠に添い寝する現在
永劫のほどに流転する閉じた宇宙の
澱んだ一室に佇むひとりの少年
少年は叫んだ
自己を信じ、個我を貫け
stray sheepの年がやってくる
感傷の鐘の音に引き摺られた僕は
まだ青き君に誓うBlue year’s sonnet
目次にもどる
ケロイドの朝
膨らんだ闇の中に佇み
蒼く茫洋たる燐光にひかれ
僕は裸足で街に出る
月に病んだ、solitude
其処で僕は無彩だった
其処には色も境界もなく
ただ誰もが傷を背負う
憑きにやんだ、sollen
僕はあぎとから逃げ出した
そう、そのあかく開かれた傷口
僕を闇中に噛みしだかんと迫る
僕は暁闇の中、屋上に待った
陽が街の全ての闇を洗う刻を
そう、陽は昇った、あかきケロイドの陽が
目次にもどる
哀願
固くて冷たい浴槽のかけらを枕にして
星空の天井に向かって僕は吐息する
赤黒い最後のぬめりが排水口を流れ
拍動を失った心臓が既に冷たい
瀕死のネオンが蒼い火花をバチバチと散らして
星空へのヴェールを掛け忘れて息絶えた
裸の宇宙が僕の全身を恥部までも覗く
宇宙の塵芥の輝きが塵芥への還元を誘う
僕の肉塊は貪欲な腐蝕をもって応えるだろう
散逸する肉体の堅固な氷の柩に僕は眠る
哀願−おねがいだ−
廃墟の街を照らす冷たい星々の輝きよ
淀みきった僕の血流の最後の一滴まで滞らせ
氷漬けの僕を串刺しにして路上にさらせ
目次にもどる
猫又の嘆き
百年の鼓動、百年の倦怠
百年の惰性を生というか?
私は黒ねずみの街に生まれ
灰色の人々の歩む通りを駆けた
酸っぱい雨音の漏れるネジロに棲み
生きる糧を求め、駆け、駆け、駆けた
しがない猫又の不幸は
渇望の二字を知っていたに
他ならなかった
飢えを満たして彷徨いつつ
渇きを癒すものを求めていた
食らった、食らった、食らった
いつも、いつも、百年も
百年を生き、まだ生きようとする
生の貪欲さに飽いていた私は
駆け、駆け、駆けた
この薄汚く愛しき街を
百年の惰性に身を任せつつ
食らった、食らった、食らった
稀薄な私の分身たちを
目次にもどる
夜光虫
騙られた自然の砂浜の上を踏むと
はるかに微小な粒の生命たちが光り
やんわりと夜闇を解き開いて
自身の存在をほのかに誇示する
騙られた砂、騙られた貝殻、
騙られた事象の中の、真物の生命
夏の夜に波音は滔々と脈動し
生命は煌々と輝きを増す-noctiluca-
目次にもどる
BIRTH
瑪瑙の月が
colorfulな斑紋を拡げて
あの子が旅に出る
引き裂かれる引き裂かれる
母胎が引き裂かれる
記憶が引き裂かれる
揺籃の記憶
月の満ち引きのリズム
ドンドコドンドコ
柔らかい臓腑のリズム
あの子が旅に出た
何処に旅に出た
瑪瑙の斑紋を引き裂いて
つめたい娑婆に旅に出た
目次にもどる
Tear
オマエがその存在を叫ぶとき
私はオマエを否定しているのだ
私はオマエほど弱くはないと
同じくらいに叫んでいるのだ
オマエがいなくなったなら
私もきっといないだろう
目次にもどる
閉ざされた教室
暗闇で閉ざされた
教室はプラネタリウム
漏れ日は天の川
壁の汚点は恒星の数々
むかし、この宇宙には
あまたの息吹が聞こえた
歓声がこだました
郷愁の遠い宇宙
子どもらはこの宇宙のものに
神が宿ると信じた
小さくて軽い宝物の神々
それらは今や見捨てられ
宇宙の風化に耐えている
静かに宇宙は耐えている
漏れ日は天の川
壁の汚点は恒星の数々
静かに宇宙は耐えている
詩集「錯綜」89−92
発行者 永一直人(地碧星)
編集
1992年12月 1日初版発行
1999年 4月 5日第4版発行
ホームへもどる
自作詩集へもどる
目次にもどる