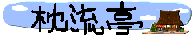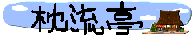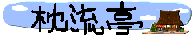
夏姫をめぐる物語とその周辺
このページは、中国の春秋時代に実在した女性・夏姫について枕流亭主が書いた文章です。亭主の昔の卒論の文章をもとにしています。
けっこう長文ですので、ヒマでないかたは夏姫夜話の概略を読むか、枕流亭ホームに戻られることをオススメします。
[夏姫とは、また悪女とは]
まず簡単すぎる紹介でお許し願いたい。
夏姫(かき)は中国の春秋時代中期に実在した女性のひとりで、列国の公卿や大夫の閨房に侍った悪女とされてきた人物である。
中国の歴史には、古代から数多くの「悪女」が登場した。いまだ伝説時代に属する女性-嫦娥、夏の妹喜ら。歴史時代以降の女性-殷の妲己、周の褒ジ、晋の驪姫など、枚挙にいとまがない。このことは、近代以前の中国社会で女性の地位が不当に貶められてきた歴史と無関係ではない。先史以前の中国社会が母権制社会であったとする説もあるが、少なくとも文字に記された歴史時代以降の中国社会は、あくまで男性中心の社会がつづいた。
男性中心の社会は、男性中心の歴史記述を生む。「文字の国」中国の歴史記述は紀元前のものに限っても厖大なものだが、女性をめぐる記述はその一部をなすにすぎない。だが、男性中心社会も社会の半分を構成する人々を無視することはできなかった。女性を支配秩序の中で価値づけることが必要となった。そのために儒教道徳が利用された。儒教は中国社会の支配秩序のために長らく貢献したが、女性のためにもひとつの鎖を用意した。それを「婦道」という。この儒教道徳は、「三従の徳」を勧め、「賢母貞婦」を称揚し、「妖女毒婦」をしりぞけた。この道徳原則は長く中国の歴史記述の上で貫かれた。
中国古代史の「悪女」記述は、この道徳における「他山の石」をになうものであり、むろん、その表現には誇張の存在も勘案しなくてはならない。だが、逆説的にいえば、その誇張された「悪」の記述こそ、抑圧された性が解放の叫びをあげる姿を見ることはできないか。
さてここで取りあげる夏姫という女性は、はたして多面的な観点に照らして悪女というにふさわしい人物なのか、それともいまわしい封建道徳が彼女にいわれなき汚名を着せたに過ぎないのか。
さいわいなことに彼女についてはいくつか史料があり、また小説作品も書かれている。そこにある夏姫像を照らしながら、見ていきたいと思う。
[夏姫の伝記]
夏姫は、鄭の公女である。父は鄭の穆公(蘭)、母は姚子という人である(『左伝』昭公28年)。
生年は、紀元前640年から630年の間と思われるが、判然とはしない。
時代は、晋の覇者文公(重耳)〈位636B.C.~628B.C.〉が薨じ、楚の荘王(旅)〈位614B.C.~591B.C.〉に覇が移ろうとしていた。
鄭は、古くは大国であったが、当時は凋落して晋楚の二大諸侯に挟まれた弱小国の地位に置かれていた。
夏姫は、成年に達すると、隣国の陳の大夫の夏御叔という男と婚姻した。
(それ以前に子蛮という男と婚姻して早死させたという記述もある(『左伝』成公2年)が、これは鄭の霊公(夏姫の兄、名は夷)と関係したことを指すとする杜預注と、夏御叔の前に夫がいたとする沈欽韓の説が対立している。)
夏姫は、夏御叔との間に、一子夏徴舒(字は子南)を得たが、夫・夏御叔は早死してしまう。
夏御叔の死との前後は不明だが、夏姫は、陳の霊公(平国)、陳の大夫孔寧(公孫寧)、同じく大夫儀行父の三者と密通した(『左伝』宣公9年、『史記』陳・杞世家)。
(だが、この行為が夏姫の主体的行為であったかどうかについては、記述がないので定かでない。)
鄭の穆公が卒し、子の霊公(夷)が立った(606B.C.)(『左伝』宣公3年、『史記』鄭世家)。
楚の人が鄭の霊公にすっぽんを献上した。公子宋(子公)と公子帰生(子家)が参内しようとすると、子公の人指し指がピクリと動いた。子公はそれを子家に見せて、
「今までこういうことがあると、必ず珍味にありつけた」
と言いながら入っていくと、宰夫(料理人)がすっぽんを割いている。二人は見交わして、笑った。霊公が笑ったわけをたずね、子家が今の話をした。大夫たちにすっぽんのスープを配る段になって、霊公は子公を呼んだのにスープを与えなかった。子公は怒って、指をスープの鼎の中に突っ込み、指を嘗めてから退出した。霊公は激怒して、子公を殺そうとした。子公は、先手を打って、子家と共謀して霊公を弑殺した。霊公の死後、鄭では異母弟の襄公(堅)が立った。(605B.C.)(『左伝』宣公4年、『史記』鄭世家)
ある日、陳公と陳の大夫二人は、それぞれが夏姫の肌着を着込んで、朝廷でふざけあっていた。大夫の洩冶が、「国君や卿の方々が大っぴらに淫らなことをなさると、民にはお手本がなくなります。それに国外への聞こえもよくありません。どうか肌着などおしまい下さい」と陳公を諌めた。すると、陳公は「私は改めよう」と言った。陳公は、二人にこの話をした。二人は洩冶を殺そうと請い、陳公がとくに止めないでいると、洩冶を殺してしまった(600B.C.)(『左伝』宣公9年、『史記』陳・杞世家)。
陳公は、株林の夏氏の家に足しげく通った(『詩経』陳風株林)。陳の政治は乱れ、周王(定王)の使いである単襄公という人は陳の滅亡を予見した(『国語』周語中)。ある日、陳公は孔寧、儀行父とともに夏氏の家で酒宴を催した。陳公が儀行父に「徴舒はおまえに似ておるぞ」と言うと、「君にも似ております」と答えた。夏徴舒はこれを聞いて憤慨して、陳公が邸から出る時、厩のかげから矢で射殺した。孔寧、儀行父の二人は楚に逃げた(599B.C.)(『左伝』宣公10年、『史記』陳・杞世家)。
翌年、楚の荘王は、陳の夏氏の乱を理由に、陳に進攻した(598B.C.)。陳の人には、「恐れることはない。少西氏(夏徴舒)を討つのである」と言って、陳に入城し、夏徴舒を殺して、栗門で車裂の刑に処した。楚王は陳を楚の県にしようとしたが、家臣の申叔時に諌められたため、太子の午(成公)を立てて、陳を復興した(『左伝』宣公11年、『史記』陳・杞世家)。
楚が夏徴舒を討った際に、荘王は夏姫を楚の後宮に入れようとしたが、申公巫臣(姓は屈、名は巫、字は子霊)は諌めた。
「いけません。君は諸侯を召集して夏氏の罪を咎められたのに、こんどは夏姫を迎え入れたりすれば、その色香に迷ったことになります。色香に迷うのを淫といい、淫は大罰を受けるもの。どうかお考え直し下さい」
荘王はそこで夏姫を後宮に入れるのをやめた。
今度は子反(公子側)が夏姫を妻に迎えようとするので、巫臣は言った。
「これは不祥の女です。子蛮を早死させ、御叔を殺し、陳の霊公を弑し、夏徴舒は誅を受け、孔寧と儀行父を出奔させ、陳国を滅ぼさせたというとんでもない不祥の女。人の生命は保ち難いもの、こんな女を妻にするとまともには死ねませんよ。天下に美人はいくらでもいます。あの女にばかり執着することはないでしょう」
子反はそこで夏姫を妻に迎えるのをやめた。
荘王は夏姫を臣下の連尹襄老に与えたが、襄老がヒツの戦(597B.C.)で殺されて遺骸を晋に奪われてしまうと、その子の黒要が夏姫と結ばれた(『左伝』成公2年)。
すると巫臣は夏姫に、「生家の鄭にいったん帰りなさい。私があなたを妻に迎えるから」と指示し、さらに鄭から夏姫を呼び寄せるよう手をまわして、「襄老の遺骸が取り戻せるから、ぜひ鄭に迎えに来てほしい」と言わせた。夏姫がそれを荘王に話し、荘王が巫臣に下問すると、こう答えた。
「きっと本当でしょう。ヒツの戦で捕虜にした知オウ(知武子)の父荀首(知荘子)は、晋の成公(黒臀)のお気にいりで、荀林父(中行桓子)の末弟に当るが、こんど中軍の佐となったところで、鄭の皇戌とも親しく、この子を可愛がっています。きっと、晋の捕虜になっている楚の王子(公子穀臣)と襄老の遺骸とを楚に返還して、代りに知オウがほしいと鄭に斡旋を頼むでしょう。鄭の人はヒツの戦で楚に加担したことを心配し、晋に御機嫌をとりむすぼうとしているから、きっと晋の依頼に応ずるでしょう」
荘王は夏姫を鄭に帰らせることにした。出発に当って、夏姫は見送りの者に言った。
「襄老の遺骸が手に入らなかったら、私は楚には戻って来ませんからね」
巫臣は夏姫を鄭から妻に迎える手筈を整え、鄭の襄公(夏姫の兄(弟)、名は堅)もこれを許した。時に荘王が亡くなって共王(審)が即位すると、陽橋作戦(589B.C.)に備えて、巫臣を使節として斉に派遣し、ついでに出兵の期日を通告させた。巫臣は家財を全部携えて出発した。
楚の大夫申叔跪は、父(申叔時)に随行して都の郢に赴く途中で、巫臣の一行に出遇い、「妙だなあ。あの人は軍事の使命を帯びて緊張しているはずなのに、かえって逢引に行くように浮き浮きしている。人の妻を盗んで逃げようとしているのではあるまいか」と言った。
巫臣は鄭に着くと、斉への礼物を副使に持ち帰らせ、夏姫を連れて鄭を立ち去り、斉に逃げようとした。しかし、斉軍が鞍の戦(589B.C.)で敗れたばかりなので、「私は敗れた国には止まりたくない」と晋に逃げ、郤至に依頼して晋の臣下となった。晋の人は、巫臣をケイの大夫に任命した。それを聞いた楚の子反は、手厚い礼物によって晋に任用を停止させようと請うたが、共王はこう言った。
「やめなさい。巫臣が自分の利害ばかりを考えていた点は、過失だが、先君(荘王)のために策謀してくれた点は、忠である。忠によって社稷を固めてくれた点は、過失を償って余りがある。それに晋国に役立つ力が巫臣にあれば、いくら礼物を手厚くしても、晋は同意するまい。もし晋に役立たぬような男だったら、晋はきっと見捨てるだろう。わざわざ任用停止を求めても仕方あるまい」(『左伝』成公2年、『史記』晋世家)
楚が宋を包囲した戦(594B.C.)の際、楚軍が引き揚げると、子重(公子嬰斉)は申・呂二県の土地の一部を賞田として分取したいと請い、荘王はこれを許した。すると申公巫臣が、「いけません。この土地は申・呂二県が成り立つに不可欠のもので、ここから出した兵賦によって北方への備えとしています。もしここを子重が取れば、申・呂は消滅するも同然。晋と鄭は必ず漢水まで押し寄せてきます」と反対したので、荘王はこれをとりやめた。子重はこのことから巫臣に恨みを抱いた。
子反が夏姫を妻としようとした際に、巫臣は不祥な女だからとそれを止めさせたのに、かえって自分の妻にした上、晋に逃げてしまった(589B.C.)。そこで子反も巫臣に恨みを抱いた。
楚が共王の時代になると、子重と子反は、申公巫臣の一族の子閻・子蕩、それに清尹琇忌、連尹襄老の子黒要を殺して、その家財を分取した。子重は子閻の家財を取得して、沈尹と王子罷とに子蕩の家財を分有せしめ、子反は黒要と清尹の家財を取得した。巫臣は怒って、晋から子重、子反の二人に書簡を送った。
汝ら、邪悪・貪欲の心もて君に仕へ、無辜の者をあまた殺す。 余、必ず汝らをして、奔命に疲れ果てて死せしめん。
巫臣が呉への使者に立つことを請うと、晋の景公(拠)はこれを許した。呉王寿夢は巫臣を歓迎して、ここに呉・晋二国間の通交が開かれることになった。呉に赴く際に伴った兵車三十輛のうち、半分の十五輛を呉に残し、射手と御者も呉に与えて、兵車の乗り方、戦陣の張り方を教え、楚から離叛するよう仕向けた。さらに巫臣は息子孤庸を残留させ、呉の行人(外交官)とさせた。
呉の楚への進攻が始まった。巣を攻め、徐を攻めるたびに、楚の子重は駆けずりまわった。馬陵の会合(584B.C.)の際に呉の人が州来に攻め入ると、子重は鄭から駆けつけた。かくて子重と子反は、巫臣が書簡で言った通り一年のうちに七回もの奔命に疲れ果ててしまった。のちに子反は、エン陵の戦(575B.C.)の敗戦の責を負って自殺した。それまで楚に服属していた蛮夷は、ことごとく呉に取られてしまった。こうして大国となりはじめた呉を、巫臣は中原諸国に通交させたのである(『左伝』成公7、16、襄公26年)。
夏姫の晩年は史書に明らかではない。ただ、後年に巫臣と夏姫との間に生まれた娘が、晋の大夫の叔向という人に嫁したという記述が見られる(『左伝』昭公28年)。
[史書における夏姫像]
Ⅰ.『春秋左氏伝』における夏姫描写
『春秋左氏伝』は、孔子の編纂になるといわれる春秋時代の魯の年代記『春秋』(五経のひとつ)の「伝」(解説)である。
(『春秋』の伝は、『左氏伝』『公羊伝』『穀梁伝』をもって「春秋三伝」と称し、また『胡氏伝』を入れて「四伝」とも称す。
『左氏伝』はその中にあって最も史話が豊富である。左丘明の著といわれるが、この人は生没年、経歴など不明のところの多い人物であって、はっきりとはしていない。)
夏姫の歴史記述は、史書のうちこの『春秋左氏伝』(以下『左伝』と略す)の記事が最も詳しい。
『左伝』ほかの史書の記述を拾い集めるのが、じつは前章の夏姫の伝記であった。
『左伝』の記述上から結果倫理的な夏姫の「悪」を発見することは容易である。一公二卿との姦通、義子黒要との姦通、洩冶の死、陳公の死、実子夏徴舒の死、巫臣の一族の死、陳・楚の傾国などの「悪」を指摘することができる。また、『左伝』の筆者自身の言葉ではないが、巫臣の評言として「是不祥人也」(成公2年)、叔向の母の言として「吾聞之、甚美必有甚悪」(昭公28年)などの夏姫の悪女評価が聞こえてくる。
しかるに、夏姫には夏姫の「悪」を裏打ちする自発的行動がない。つまり『左伝』の夏姫には、夏姫の主体的な行動がない。実はあるのかも知れないが、それと明示されていないため、夏姫の主体性や動機倫理的な「悪」は見えていない。主体的に行動しているのはいつも夏姫に関わる男たちであり、勝手に破滅しているのもやはり男たちである。
さらに夏姫には主体的に発した言葉がない。『左伝』の記述における唯一の夏姫の言葉は「不得尸、吾不反矣」(成公2年)であるが、これは巫臣が言わせた言葉である。
善悪の評価において、動機倫理、結果倫理、責任倫理の3つの立場があると言われる。『左伝』を材料にして、結果倫理をもって語れば、幾らでも夏姫を断罪することは可能である。先に挙げた巫臣や叔向の母の言も、この結果倫理による批判である。だが、動機倫理でもって語れば、とりつく島もない。夏姫の心情は一切『左伝』に明らかにされていないのだから。この倫理で夏姫を悪と断じることができるとすれば、次節の『列女伝』のような強引な論理が必要になる。
『左伝』の夏姫の「悪」を責任倫理の立場で明らかにできるだろうか。まず夏姫の姦通については、「悪」と見ることもできる。だが、夏姫の非主体性から見て、強制的状況があったと見て、夏姫には責任がないと弁護することもできる。いずれにしても明確な判断を下す材料はない。夏姫の姦通から派生する洩冶の死、陳の霊公の死、夏徴舒の死、陳の傾国、巫臣の一族や黒要の死などは、根元がはっきりしない以上、夏姫を「悪」と断じえない。むしろ責任倫理と言うのならば、それらに関わった男たちの方が、より主体的で明確な責任があり、「悪」と明言しうる。
もともと『左伝』の念頭の中心にあったのは、夏姫の行為の善悪理非ではなく、男性「主体」の行為の理非にあったと思われる。洩冶、荘王の行為(宣公9、11年)は、孔子の言葉や『詩』(大雅板)の引用などをもって筆者自身の評価の記述がある。だが、夏姫に対する筆者の評言はない。『春秋』の各伝やさらに各伝の弁疑等でも、夏姫の「悪」はさほど問題にされていないようである。
Ⅱ.『列女伝』における夏姫描写
『列女伝』は、前漢に成立した婦道の本である。唐虞以来の女性の伝記を集成している。劉向の撰で、七巻よりなる。七巻の目は、母儀・賢明・仁智・貞順・節義・弁通・ゲッ嬖とある。各巻に小序と十五伝がつく。
夏姫のエピソードは、七巻「ゲッ嬖伝」の「陳女夏姫」の項に収録されている。まず、「ゲッ嬖」の意味であるが、ゲツは「不吉な、わるい」の意であり、「嬖」はヘイと読み、「貴人に愛される女性、もしくは男性」の意であって、合わせて「ゲッ嬖」はゲッペイと読み、「悪女、妖女・毒婦の類」の意である。『列女伝』は、はじめて筆者自身の言葉で夏姫を「悪女」の範疇に入れた書といえる。
荒城孝臣注解『列女伝』の「陳女夏姫」の伝から特徴的な部分を抜き出すことにしよう。
まず、「陳女夏姫とは、陳の大夫夏徴舒の母なり。その状 美好にして匹無く、内 技術を挟む。蓋し老してまた壮なる者なり。三たび王后となり、七たび夫人となる。公侯これを争ふもの、迷惑失意せざる莫し」を挙げよう。
この部分は、『左伝』等にはない夏姫の特徴を伝えている。下見隆雄『劉向『列女伝』の研究』(東海大学出版会)によれば、この「内挾技(伎)術」は、「ひそかにわかがえりのすべをたしなみて」と読んでおり、「蓋老而復壮者」と合わせて、夏姫が「神仙方伎の道を体得した女性」であったかのように伝えているとする。下見によれば、『列女伝』の異本には、「夏姫挾技術、老而復少者三、諺曰、夏姫得道、ケイ皮三少」とあるという。老いて三度若返る「老而復少者三」の夏姫は、次章の海音寺の「妖艶伝」の夏姫につながるし、神仙秘術をたしなむ「夏姫得道」の夏姫は、駒田の『夏姫物語』の夏姫につながっていく重要なイメージである。『列女伝』において、明らかに筆者劉向は夏姫の「悪女」イメージの増幅を行なっており、「三為王后、七為夫人」の真偽はともかく、「公侯争之莫不迷惑失意」で、夏姫の「悪女」のイメージは確固としたものになるのである。
次に、「公孫寧・儀行父と、陳の霊公と、皆夏姫に通ず。或ときその衣を衣て、以て朝に戯る。泄冶これを見て、謂ひて曰く、『君 不善あれば、子 宜しくこれを掩ふべし。今、子より君を率ゐてこれをなし、幽間を待たずして、朝廷において以て戯る。士民それ爾を何と謂はん。』と。二人以て霊公に告ぐ。霊公曰く、『衆人 吾の不善を知るも、害なし。泄冶これを知るは、寡人恥づ。』と。乃ち人をして微かに泄冶を賊してこれを殺さしむ」を挙げる。
この部分もまた、『左伝』の記述と異なる。『左伝』においては、洩冶が霊公を諌め、霊公が二大夫にそれを話して、二大夫は洩冶を殺そうと言い、霊公が止めなかったために、二大夫が洩冶を殺したことになっている。対して、『列女伝』においては、泄冶(=洩冶)が二大夫を諌め、二大夫がそれを霊公に告げ口して、霊公は泄冶に知られたことを恥じて、人に命じて殺させたことになっている。この差は、洩冶殺しにおいて、霊公と二大夫のいずれがより主体的であったかが逆転している。なお、『穀梁伝』は、『列女伝』に近く、「君愧於泄冶不能用其言而殺之」(宣公9年)という記述があって霊公が洩冶を殺したこととなっている。
最後に、「詩に云ふ、『乃ち之の如き人は、婚姻を懐ふなり。大いに信なきなり、命を知らざるなり。』と。嬖色は命を殞すを言ふなり。/頌に曰く、夏姫好美にして、国を滅ぼし陳を破る。二大夫を走らせ、子の身を殺す。殆んど楚荘を誤らんとし、巫臣を敗乱せしむ。子反悔い懼れ、申公の族分たる」を挙げる。
これが、夏姫の「悪」を強調していることは、言うまでもない。『詩』(ヨウ風テイトウ)の引用部分を訳すと「このような人は、男欲しさに結婚を思うのだ。婦道の信(まこと)はない、女の天分をわきまえぬ者なのだ」となり、婦道の信を盾に、夏姫の動機倫理的な評価にまで踏み込んでいる。また、「頌」の部分では、陳の亡国や男たちの破滅について、結果倫理的に(解釈次第では責任倫理的にも)断罪している。
また、『左伝』との違いとして「敗乱巫臣」の部分が気になるところだが、山崎純一『列女伝 歴史を変えた女たち』(五月書房)にある次のような文を見れば分かるだろう。「劉向は、この巫臣の復讐譚をきりすてて、賢者巫臣を楚の叛逆者たらしめず、痴愛の女の魔性に、ついに悲劇にひきずりこまれた、不運の人として描ききったのである」。あくまで夏姫の「悪女」性を強調したいのである。
対して、先に挙げた下見『劉向『列女伝』の研究』は、「悪女」評価でないとする見解である。「作者は悪の主体を夏姫に置いている様には思えない」というのである。他にも「夏姫は悪を意識的積極的に作り出す存在ではない。近づく男たちが女性エネルギーに巻き込まれ自滅するのである」、「この夏姫は『列女伝』の主人公にしては珍しく主体的生活理念を持たぬ」のように述べている。史料を列挙した上での夏姫評価としては、同感であるが、『列女伝』の筆者劉向がそう考えていたかどうかは甚だ疑問である。たとえ考えていなかったとしても、劉向の強調したかったのは、主体的「悪女」としての夏姫であろう。
『列女伝』における「悪女」のレッテルは、次章に論じる「歴史小説における夏姫像」にも長く強い影響を与えるのである。
[歴史小説における夏姫像-作家の想像が生み出す虚構の発展-]
Ⅰ.中島敦「妖氛録」(>『中島敦全集3』(ちくま文庫))における夏姫像
中島敦「妖氛録」は、夏姫を題材にした日本の小説的作品の最初のものと思われる。そして、夏姫をモチーフとした作品の中で最も短い。
ただし、この作品は中島の死後17年たって刊行された全集(文治堂版全集第四巻、1959・6)に初めて収録されて公表されたので、少なくとも次節に挙げる海音寺潮五郎「妖艶伝」への直接の影響関係はない。中島氏自身に発表する意図があったかどうかも不明である。しかし不思議に、中島の夏姫は、海音寺の夏姫に最もよく似ている。
まず、題意を明らかにしなければなるまい。「妖氛録」の「妖氛」は、「不吉なことの起こりそうな気配」というくらいの意味である。その題意のとおり、この小品の全編には、払拭しがたい「妖氛」が芬々としている。
「妖氛録」の夏姫は、その「妖氛」の源である。この夏姫は、「口数の寡い、極く控え目勝ちな女」(P327、L1)である。美人であるが、「毒々しい妖婦的な容貌」(P330、L11)ではなく、「案外平凡な物静かな女」(P330、L11-12)である。「自分故に惹起される周囲の様々な出来事」(P327、L2-3)に「誇を覚えているのか、迷惑を感じているのか、愚かな男共を嘲っているのか」(P327、L5-6)誰にも分からない。
この「つくり物のように静かな顔に、時として、不意に燃えるような華やかさの動き出すことがある」(P327、L8-9)。そんな時、「此の女は世の常の女ではなくなる」(P328、L1-2)。「斯うした時の此の女を見た少数の男だけが、世の常ならぬ愚かさに我を忘れ」(P328、L2-3)てしまうのだった。
この小説は、『左伝』の記述を周の年号に直して、かなり忠実になぞっている。その歴史記述に、夏姫の「妖氛」の叙述がまとわりつくのだ。そのまとわりつく「妖氛」が、作者中島の創作部分なのだが、その「妖氛」は、純粋な歴史記述とすでに癒着してしまって離れない。
「霊公と二人の上卿との間には、嫉妬というものが殆ど無かった。嫉妬の生じる余地の無い迄に、夏姫の周りに立罩めた雰囲気が彼らを麻痺させていたのである」(P329、L11-12)
夏姫の「妖氛」は、『左伝』の記述における四角関係が円満であった不思議を解き明かしてしまう。
やがて、夏姫は、史実どおりに巫臣と楚から晋へと駈け落ちした。「夏姫は別に大して喜ぶ風も見せずについて行」(P333、L5)く。夏姫は、「巫臣の室として、落ちつ」(P334、L2)く。その姿は、「嘗て陳楚二国を擾がした妖姫とは、どう見ても受け取れない」(P334、L3)。巫臣は、夏姫の貞淑に猜疑を抱かずにいられない。そして、「貞淑な夏姫が家に来てから、頓に索漠となった身辺を顧みて」(P334、L12)、愕然とせざるをえないのである。
巫臣は、「如何に自分の運命がこのものの為に高い価を払わなければならなかったかを(中略)マザマザと感じた」(P335、L2-3)。そして、「わけの判らぬ妙なおかしさが込み上げ」(P335、L3-4)、「しまりもなくゲラゲラと笑い出した」(P335、L7)のである。
巫臣のこの笑いは、わけの判らぬ「妖氛」に翻弄された自分に対する自嘲の笑いである。その「妖氛」を発する源にみえる夏姫も、「所詮は操られたにすぎぬ」(P335、L4)存在でしかない。操りの主は、歴史というやはりわけの判らぬものであろう。
この小説は、歴史を描いた作品でありながら、幻想小説のような妖しさを持っている。それがつまり「妖氛」であるのだが、その「妖氛」は、ある種の雰囲気であって、同じ中島の作品での「山月記」の虎(李徴)のような直截的な表れはしていない。つまりこの小説には、「山月記」のような非現実的なキャラクターや設定は存在しない。だが、「山月記」に通底するものがここにひとつある。それは「不条理」である。
「山月記」が、カフカの不条理小説「変身」を翻案していることは知られているが、この「妖氛録」でのテーマも不条理といえよう。夏姫たちを翻弄する「妖氛」は、歴史の、人間の、無常感とか不条理とも言い換えることができる。だから、その「妖氛」テーマの前に、夏姫の「悪」とか主体性とかは問題にならない、というより、そういうものを超えて語らざるをえないのである。
作者中島が、この「妖氛」によって、夏姫たちを人間の「悪」から免責しようというのか、それとも操られるにすぎぬ彼らを貶めようというのか、そのどちらにも解することができる。そのどちらにしろ、あまりにも無力な人間はただ巫臣のごとく笑うしかないし、だからといって何ら救われるわけでもないのである。
Ⅱ.海音寺潮五郎「妖艶伝」(>『中国妖艶伝』(文春文庫))における夏姫像
海音寺潮五郎「妖艶伝」は、『小説公園』1954年6月号に初めて発表された中篇である。その主人公は夏姫ではなく、申公巫臣である。「楚の賢大夫」を自負していた巫臣の夏姫に対する心情の変転を中心に、やがて悲劇にいたる経緯を『左伝』の記述をもとに描いている。
ストーリーは、夏徴舒が陳公を弑し、それに対して楚がどう対応するかをめぐる会議の場面からはじまる。楚の大夫たちの興味は、事件の発端たる夏姫に集中する。夏姫の経歴、年齢、その美しさが話題になる。「四十がらみの女」「嬋娟窈窕」「天性の淫婦」といった言葉が回転し、大夫たちは未だ見ぬ夏姫の「妖艶」にとらわれている。巫臣は、なみいる楚の大夫たちを惑わす「妖艶」な雰囲気と夏姫とに反発を抱いた。巫臣は「楚の賢大夫」なのだ。
楚が夏徴舒を討った後、捕えられた夏姫を荘王は後宮に入れようとし、子反は妻に所望する。これに対する巫臣の諌言は、後に夏姫を得るためにした陰謀とはつながっていない。海音寺の巫臣がここで諌言するのは、「楚の賢大夫」としての真情ゆえである。 その真情が一変するのは、巫臣が夏姫を垣間見た後である。「その女には、一見して人の心を奪う美しさはなかった。いささか黄みおびた青白い、小さい顔といい、憂わしげに伏せられた目といい、また、女としては少し身長がありすぎはしないかと思われる体は、細っそりしすぎており、いくらか病的な感じさえあった」(P41、L9-11)
「しかし、歩きぶりの美しさが、はげしく巫臣をひきつけた」(P41、L12)「暁の風にめざめて身ぶるいする露をおびた蓮華の風情、春の微風にそよぐ若い柳の嫋々さがあった」(P41、L15-16)
「不思議なものだ。そう気が付くと、女の全貌がまるで違って見えはじめた。痩せていると見えたのは、骨組みが華奢で、すらりと長身であるからで、実際はゆたかな肉おきらしく、胸のあたりも、腰のあたりも、やわらかなふくらみに悩ましく息づき、わけても、やや長目の真直ぐな頚は、艶やかな白さをもって丸く張り切っている顔色もかすかな黄みを帯びた青白さであるが、決して単純な不健康な色ではなかった」(P41、L17-P42、L2)
「彼は、夏姫の年のことを考えてみたが、全然その年に見えなかった。と言っても、若くも見えなかった。年のない感じだった。/『不祥な女だ。妖婦だ』/またしても、微かな震えを背筋に走らせた」(P42、L15-18)
巫臣は夏姫を「不祥な女」と言いながら、夏姫のことを思い眠れなくなる。夏姫の「不思議な魅力」を肯定したとき、夏姫を枕頭に侍らす荘王や夏姫を妻にした襄老に嫉妬を覚えずにいられなくなった。その感情は、「恋という優雅な感情」(P49、L17)ではなく、「相手をひっつかんで、ねじ伏せて、出来るだけ残酷に犯したいという酷烈な欲情」(P49、L18-19)である。巫臣はこの感情を否定しえず、夏姫を得るための謀略をめぐらすことになる。やがて「楚の賢大夫」の名を捨て、晋に亡命するのは『左伝』のとおりである。
対する夏姫であるが、作者は「悪女」と規定していない。「夏姫は気弱で、さびしがりやであった。彼女のこの性質と、その美貌とが、彼女の数々の不幸を生んだ。美しかったから多くの人に愛せられ、気弱であったからその恋情を拒むことが出来ず、さびしがりやであったから、人に愛せられていなければ、一日もいられなかった」(P45、L4-7)と、夏姫の美しさ、孤独感が不幸や悲劇の原因としている。
「この性質を世間では多情だと言い、淫乱だというかも知れない。しかし、彼女は決して姦悪な心をもった女ではなかった。美貌や、男の恋情を、自分の利益のために利用しようというような腹黒さや、ましてや、世をかき乱して、人の不幸や、世の災厄を造ろうというような恐ろしい心は、露ばかりもなかった」(P45、L10-13)という夏姫は決して動機倫理上「悪女」ではありえない。
しかし、『左伝』にかなり忠実に進行させながら、最後に夏姫の多情描写は『左伝』を超えてしまう。二人で晋に亡命し、巫臣の復讐が終わると、巫臣は病床についた。夏姫は五十歳を越えてまだ美しく、巫臣の独占欲は萎えてはいない。夏姫は巫臣に同情し、「あたくしは、あなたに万一のことがあったら、生きてはいません。一緒に死にます」(P93、L4)と言う。
だが夏姫は、「わしは一人で死にたくない。そなたを残して死にたくない・・・約束だ。今日だ。約束だ。……」(P95、L4-5)と叫ぶ巫臣を突きはなしてしまう。そして、愛する夫の死のそばから巫臣の子孤庸のことを想って、「自分がまだ美しいのがうれしかった」(P96、L2-3)わけである。
海音寺の夏姫は、動機倫理的な「悪」を明確に否定した代わりに、積極的主体性のあまりない春秋学的な伝統夏姫解釈を踏み越えていない。この夏姫は、目的意識的に何らかの行動を起こすことはない。
また、この夏姫は動機倫理的に完全にイノセントなわけでもない。夏姫の多情さは、孤庸への思慕等の創作エピソードで強調されている。さらに、「自分がかわいそうでならなかった」(P95、L15)、「こんなにこの人を愛し、こんなにも忠実につくして来た自分なのにと思った」(P95、L16)などに無意識的な自己愛が顕れている。この夏姫には、前節の中島「妖氛録」の夏姫のような非人間的不気味さはなく、欠点も明け透けで、非常に人間的に描かれている。
さて、前節で「中島の夏姫は、海音寺の夏姫に最もよく似ている」と書いたが、その類似点は、夏姫の動機倫理的「悪」を問題にしない、もしくは否定することで、悲劇の原因を「妖氛」だとか「妖艶」だとかに還元してしまっていることである。そして、夏姫という女性の主体性を貶めたままにしていることである。それは確かに歴史事実に沿い、「歴史其儘」により近しいことなのかも知れない。しかし、夏姫をめぐる物語は、取り上げる四作品の中で、時代が進むにつれて、夏姫という人物の主体性を「救済」する方向へ創作されていくことになる。その途上にある中島や海音寺の作品はやはり「古い」作品に属するのである。
Ⅲ.駒田信二『夏姫物語』における夏姫像(>『夏姫物語』(徳間文庫))
駒田信二『夏姫物語』は、1975年12月に、現代企画室より書き下ろし発表された長編小説である。駒田は、『史記』や『列女伝』にあらわれる夏姫をめぐる一連の物語を、夏姫の性愛の遍歴物語としてとらえた。彼女は「吸精導気の術」なる秘術を身につけて男性エネルギーを吸収し、若さを保つ「得道」の存在に仕立てたのである。
夏姫は、笄年を迎えた夜、「頭に星冠をいただき、身に羽衣をまとった道士らしい偉丈夫」に抱かれ、「吸精導気の術」を授けられる。「吸精導気」とは、男性の陽の気を吸収して女性の陰の気を補い、いつまでも変わらぬ若さを保つ秘法と説明されるが、むろんこれは創作である。
その夢のような夜から醒めた翌日から、夏姫は淫奔な妖女に変身した。兄の公子蛮(駒田の説では、後の鄭の霊公=夷とは別人)と交わり、精を吸い尽くして、二年そこそこで夭死させてしまう。続いて兄の公子夷(後の鄭の霊公)や公子公と次々と関係していく。なお、この三角関係による確執は、後に起こる子公の霊公弑殺事件の伏線として説明されているのである。
この兄妹の相姦および兄弟の相克が、重大な結果をもたらすのを恐れて、父の穆公は夏姫を隣国陳の大夫夏御叔のもとへ嫁がせようとする。ここで、夏姫が穆公の実の子ではないこと、笄年の夜の偉丈夫が実は穆公であったこと、という重大な二つの事実が明かされる。そこで再び偉丈夫穆公と夏姫は結ばれ、夏姫は処女に戻る法を得て、夏御叔に嫁いでいくのである。
夏御叔は、夏姫を得てやはり夭逝した。父の穆公は病死し、跡を継いだ兄の霊公夷は、子公に弑された。亡夫の葬儀をすませた夏姫は、夏家の領邑の株林に引きこもる。株林において、夏姫は、夏家の下男、侍女たち、孔寧、儀行父の二人の大夫、陳の霊公平国らと自由な性を謳歌する。
洩冶は二人の大夫に殺され、霊公は夏徴舒に弑された。南方の大国楚は、弑逆者夏徴舒を討ち、そのため夏姫は楚に連れ去られる。駒田の夏姫は、楚の荘王の前で次のように語ってみせる。
「徴舒はわたくしを監禁していたのでございます。いずれわたくしは息子に殺される運命だったのでございます。陛下はわたくしをそういう運命から救ってくださいました命の恩人でございます。わたくしを如何ようになされましょうと怨みはございません」(P216、L11-13)
夏姫は楚の荘王、連尹襄老父子らと次々と関係し、最後に屈巫(申公巫臣)と結ばれ、「偉丈夫さま!あなたでしたの」(P244、L12)と叫ぶラストを迎えるのだ。
清水信の解説の言を借りるに、駒田の夏姫が「悪女であったことは間違いない」。主体的に姦淫にふけり、その結果派生した息子の横死さえも顧慮しない夏姫は、動機倫理的にも「悪」に描かれたというしかない。
同じく駒田信二に『世界の悪女たち』(文春文庫)という悪女をめぐる論集があるが、この論集にも夏姫は収録されている。この論集のあとがきに駒田は、「『性質のよくない女』とか『顔の醜い女』とかいうだけの『悪女』は、私の『悪女たち』の中には一人もいない。だいいち、そんな程度の『悪女』は私にとってなんの魅力もないからである」と書いている。これは、駒田の「悪女」積極肯定ともいえる。駒田『夏姫物語』も、清水の言を借りれば、「天与の資質に忠実に生きた女性を描くこの物語の中へ、何の教訓じみた考えをもさしはさんでいない」(P249、L16-P250、L1)のであり、「大らかな性の賛歌」(P250、L2)となっているのである。
駒田の夏姫の評価は、『列女伝』にあらわれる夏姫評価と極似している。ただ、その「悪」への態度が、対極にあるだけである。『列女伝』は、その儒教道徳のために、夏姫に「悪」を発見し、夏姫の「悪」や主体性や人格を徹底して指弾しなければならなかった。だが、駒田の『夏姫物語』は、旧道徳を否定する現代性ゆえに、夏姫の「悪」や主体性や人格を積極的に肯定していくほかないのである。
駒田の夏姫において、むろん男たちも単なる被害者ではなく、主体的に「姦悪」にかかわっていく存在である。駒田は、彼ら彼女らの「悪」やその自業自得ともいえる破滅を大らかに肯定することで、人間とその歴史とを包括しているのだ。
『夏姫物語』は、史話の「悪女ばなし」としての積極的な捉え返しとエンターテインメントとしての虚構創作による物語だったと言える。作者駒田は、夏姫の「悪」を積極肯定することで、夏姫という女性の主体性を歴史の没主体的な闇から救済していったわけなのである。
さて、駒田が積極肯定した「悪」さえ否定して、夏姫を歴史の檻から解放するためには、次に挙げる宮城谷の『夏姫春秋』を待たなければならなかった。
Ⅳ.宮城谷昌光『夏姫春秋』(>『夏姫春秋』上・下巻(海越出版社、のち講談社文庫))における夏姫像
宮城谷昌光『夏姫春秋』は、1991年4月に書き下ろされ、海越出版社より発刊されている。この長編小説は、夏姫をめぐる史話がベースではあるが、より広く春秋時代の一局面での列国史話となっている。晋楚の争覇、圧迫される陳・鄭・宋といった国々、そういう時代状況の中で生きぬく多様な人間たちを描いたところにこそ、この作品の無視できないテーマがある。だが、ここではあえて拙論の主旨に沿って、夏姫を中心に見ていくことにする。
ストーリーは、宮室の不倫からはじまる。「十歳を過ぎたばかりの夏姫の寝所に忍んできた」(上P7、L10)のは、兄の子夷である。その夏姫の様態は、「非常に素直なところがあり、しかしながら人倫はどこかに置き去りにされているようで」(上P8、L8-9)あり、「春秋時代の『妖花』とよぶほかない」(上P8、L1-2)のであり、「まるで男の精気を吸うたびに成長するこの世ならぬ植物のようで」(上P8、L10)ある。
血のつながった兄に「女の性を鑿開された」(上P7、L10-11)夏姫は、子宋、子家の二人の鄭人と交わることとなる。これが、鄭の霊公暗殺に関わる伏線となるのは、駒田と同様である。
夏姫の父の穆公は、「閨門のさわがしさをきらい」(上P12、L1)、夏姫を陳の夏御叔のもとへ嫁がせることにする。この「慶事」に、子夷は逆上して騒ぎ、夏姫は涙を浮かべることとなる。
さて、夫となる夏御叔は、妻となる夏姫を一瞥して浮かれ騒ぎ、夏姫を溺愛することになる。夏御叔の父の子夏は、夏姫の「妖美」に不吉を感じ、「もしも、この女をみる者のすべてが、魅せられるとすれば、わが家の不幸は、この女からはじまる」(上P37、L7-8)と予見する。この予見はのちに的中し、少西氏(子夏の族)は徴舒の代で断絶することになる。ちなみに、この子夏の言はむろん創作だが、このような賢人の予見をのちに的中させるのは、『左伝』などの中国史書の手法のひとつであり、宮城谷はよくこれを用いている。
その子夏は没し、入れ替わるように夏姫は男児を生む。夏徴舒である。
ようやく一家の体をなした感の夏氏の家であるが、主人の御叔の機嫌は思わしくなくなってくる。御叔は、夏姫を愛すれば愛するほど、彼女が「遠ざかりつつあるような、ふしぎに満たされぬおもい」(上P58、L12)に捉われる。どこから来るのか分からない「寂寞」(上P58、L13)のためにあせり、体に変調をきたしてしまうのだ。
御叔は、「夏姫がほんとうに愛しているのは、ちがう男ではないのか」(上P64、L15)という払拭しがたい疑念を持つ。そして儀行父のヨウ(側妾)の施氏への不倫の愛を抱きつつ、病疾のために夭死する。夏姫は徴舒を連れ、陳都を離れ、夏氏の采地に引きこもることになった。徴舒は、夏氏の家宰の末子の季暢とともに育てられていく。
その後、鄭において、父の穆公が没し、兄の子夷が霊公夷として即位する。しかし早くも翌年に、夷は、子宋と子家の二卿に弑されてしまう。陳の田舎で息子の養育だけに心をかけている夏姫にも、鄭の波乱の波はかぶさってくる。後ろ盾を失った夏姫に、徴舒が成人するまで、夏氏の食邑を返還するよう、陳の政庁に通達されたのだった。夏姫は、ただひとりの息子と夏氏に忠実な家宰の一家以外に寄る辺のない無力な地位に置かれてしまうのである。
その夏姫に、さらなる不幸が襲ってくる。夏氏の家宰が冤罪を着せられて投獄されてしまったのだ。夏姫は、恩義を受けた夏氏の家宰を救うために自らの身を投げ出す決意をして、儀行父を頼り、そして彼の強要に応えて関係を持つことになる。「命をさしあげると申したのです。ほかに何を吝しみましょう。(中略)もしあなた様の言が妄であれば、わたくしは門前で縊死し、あなた様の子々孫々まで祟ります」(下P11、L7-9)と儀行父に賭命の決心のほどを語ってみせる夏姫は、駒田の夏姫とは正反対の犠牲精神の持ち主である。
その夏姫は、さらに孔寧とも関係をもつことで、家宰を釈放させることに成功する。それから「夏姫は一変した。いや、人格も変わったかもしれない」(下P15、L2)という変貌を示す。二大夫との関係を続けることで、陳都の夏氏の旧宅を取り戻し、息子徴舒の陳都の学校への入学を認めさせる。さらに、陳公に肉体を求められた夏姫は、もう拒むことができなくなっていた。
陳公と夏姫の倫ならぬ関係は、『詩』にも歌われ、陳国の悪政は他国にまでも伝わっていく。息子の徴舒は晴れて成人し、大夫となることができたが、夏姫はその息子に白眼視されるようになってしまう。
そして、破局が訪れる。大夫洩冶は陳公に諌言して、二大夫に殺された。徴舒は、その出生を陳公らの冗談口の種にされて激怒し、陳公を弑殺した。徴舒は陳公位を纂奪し、一年と五ヵ月の間、善政を維持するが、楚の荘王の軍に敗れて自刃してしまう。そして死体は車裂の刑に処されることになる。これらの一連の事件描写は、『左伝』が基本となっているが、他の三作品と比べてはるかに人間描写が細に穿っている。
一方、夏姫は、自分の息子によって陳の宮廷に軟禁されたあげく、息子の死後は楚に送られることになった。彼女は、「自分の生き方をふりかえってみた。すべてが、やむをえなかった。だが、子南もやむをえず陳公を弑したのであろう。自分のやむをえなさが、そうさせたのならば、自分はなんと罪深い女であろう」(下P73、L5-7)「なぜ、自分は人を不幸にし、自分も不幸なのだろう」(下P101、L7)と自問する。そして息子に先立たれ、涙さえも涸れはてた夏姫は、食を拒否して餓死しようとするのだ。
そんな夏姫の目の前で、ひとりの稚児が池に溺れるという事件が起こる。夏姫は、その稚児にわが子徴舒の面影を重ね、無我夢中で助けてしまう。実はその稚児は、楚の王子審(のちの共王)であった。夏姫は、「はじめて自分の手が人を助けたという実感」(下P105、L1)を得た。この実感は、夏姫を自殺から救うこととなる。
陳国は再興され、楚に連れてこられた陳の女性たちの大部分は帰国していったが、夏姫は楚に留め置かれる。荘王が夏姫に比類ない美しさを認めたからだった。荘王は、後宮に入れたいと思いながらも、夏姫の処置に迷う。陳から亡命してきた儀行父から、以前に「夏姫は風を湧かす」(下P82、L9)という話を聞いていたからだ。荘王は「どうやら夏姫には、風伯が宿っているらしい」(下P106、L1-2)と考え、その吉凶を巫臣に占わせることにした。荘王は一糸まとわぬ夏姫の胸に巫臣の耳をあてさせてみる。巫臣は、耳に風を感じて驚愕する。そしてその風声の吉凶を問う王の意図を察し、心中の動揺を押し隠して、「凶」と答えた。巫臣は、夏姫を一瞥して、どうしようもなく惹かれてしまったのである。
荘王が夏姫を諦めた後、今度は公子の子反が、夏姫の下賜を望んでいることを巫臣に話した。「夏姫は童女だ」(下P146、L5)と感じている巫臣は、子反が夏姫を玩弄する姿を想像して反発する。「夏姫は、不祥の人です」(下P146、L15)と言って、夏姫をめぐる男たちの不運を子反に語り、脅しすかした。子反を退散させて、巫臣は夏姫の悲しげな美貌を頭に浮かべ、「夏姫を幸せにできる男は、この世で自分しかいない」(下P147、L15)との想いを強くするのだった。
夏姫は、連尹襄老のもとに嫁がされた。この醜貌の老人を好きになれない夏姫は、老人に苛責され、その虐待に耐えかねて、「あなたは、死にますよ」(下P156、L15)という叫びをあげる。その不吉な予言は的中し、襄老はヒツの戦いで戦死するのである。夏姫は、自分に触れる男たちが、次々に滅びていくことに悩む。だが、遺骸のない夫の葬儀の後、夫の息子黒要が、夏姫の室にやはり忍んでくるのである。
黒要と巫臣との間が、急速に接近する。黒要にとっては、父の連尹の職を継ぐための工作であった。また、巫臣は、おかげで夏姫と近づくことができた。初めて語り合った二人は、お互いの存在に共感しあう。巫臣は夏姫を得るための策略を巡らし、そして夏姫は巫臣の気持ちを知ることになる。夏姫は巫臣に救いを求め、巫臣は彼女を不幸から救い出すことを約束するのである。
夏姫は、「襄老の遺骸を取りもどせるから、鄭にまで出向きなさい」(下P260、L17)と鄭に言わせるという巫臣の計略により、楚を出国することができた。巫臣は、斉への使者の任務を途中で放棄して、鄭で夏姫と合流した。
この駈け落ちだけでは、巫臣の計画は完成しない。巫臣は、夏姫と結ばれた男たちのように破滅していくわけにはいかないのだ。巫臣は男たちの破滅の理由を考える。そして、夏姫が本当には生まれていない-夏姫が生まれたときに当然経るべき魄を魂に変える手続きを省かれている-ということに気づく。だから、本来存在しない夏姫と結びついた者は、存在しなくなる。これはむろん巫臣の論理だが、春秋時代の神祇官の論理としてはリアルだ。そうして夏姫は、巫臣の手により新たに生まれかわる。巫臣と夏姫は晴れて夫婦となるのである。
二人は、晋に亡命した。巫臣はケイ邑を与えられ、二人は厳しい環境ながら幸せな日々を過ごす。楚において子反が子重を誘って巫臣の一族を滅ぼすという事件が起こった。ことを知った巫臣は復讐のためにケイを去り、呉との通交に赴く。復讐が終わって、巫臣はケイに帰ってきた。夏姫と巫臣を慕う夏姫の侍女が、巫臣を迎えに出てくる。遠くから樹下の二人を眺めた巫臣は、どちらが夏姫で、どちらが侍女か、風伯はどちらの女に宿っていたのか、という妙な考えを浮かべながら近づく。彼は、夏姫を抱きかかえて車に乗せ、侍女をも抱きあげる。そして、「賀いだ、祝いだ」(下P280、L5)と叫ぶ一団が遠ざかっていき、「樹下にそろりと風が立った」(下P280、L8)という印象的なラストを迎えるのである。これは、夏姫の物語として、最も爽やかな結末といえよう。
作者宮城谷は、この歴史上の人物に大いなる同情をもってこの作品を創作している。この小説全体が、「妖姫夏姫を神話的泥沼の中から救済しよう」(百五回直木賞受賞時の井上ひさし選評)という試みであり、「夏姫への愛の表現」(「古代中国の美女」<宮城谷昌光『春秋の色』(講談社))なのである。
したがって、宮城谷の夏姫は、悪女であるどころか、むしろ善女、聖女であるかのように描かれる。また、この夏姫は、一種苛烈な主体性も持っている。恩義を受けた夏氏の家宰を救うために自らの身を投げ出す。当時の倫常においては、報恩と貞節は、ともに義であり、忘恩と姦淫はともに不義である。だが、彼女は貞節の義を捨てて、報恩の義を取らざるをえない。その彼女は、一方の不義を越えて、現代的な義女であり、烈女である。また、息子の横死を嘆いて餓死しようとする夏姫は、もはや「悪女」でありえない。
宮城谷が、夏姫の救済にこだわる理由は、直接には明らかにされない。作者は、『夏姫春秋』を書いた動機のひとつとして、「なぜ、夏姫を撫有した者はつぎつぎに奇禍に遭い、巫臣だけがその災厄からまぬかれたのか」(「不日不月」<宮城谷昌光『沈黙の王』(文芸春秋))という問いがあったことを書いている。これは、巫臣に対しても作者が好意的な解釈をしていることを示している。巫臣の復讐譚を含む『左伝』ほかの史書からの解釈では、中島「妖氛録」のような妖女に翻弄された巫臣像や海音寺「妖艶伝」のような破滅した巫臣の姿を導きだすほうが容易である。だが、宮城谷は、巫臣をそうした破滅から救い、ひいては夏姫の幸福をも保障しているのである。作者は、この『夏姫春秋』の後日譚として、「鳳凰の冠」という中篇を用意し、夏姫の幸福な晩年を暗示するという周到ぶりである。ここはまず「夏姫への愛」という作者の表現を無条件で受け入れるしかあるまい。
さて、宮城谷の夏姫には、一貫してつきまとっているひとつのイメージがある。それは「風」である。愛する夏姫を奪われた子夷が「風が死んだ」(上P25、L14)と感じたり、逆に夏姫を得た夏御叔が「春の風のようなむすめだ」(上P30、L11)という印象を抱いたりするのが、それである。夏姫を抱いた儀行父は、風門から吹く「風」を感じて「その風に馮ることをやめた」(下P12、L9)のだし、巫臣が夏姫に惹かれる原因のひとつとなったのも、夏姫の肌から湧く「風」である。また、荘王は、「どうやら夏姫には、風伯が宿っているらしい」(下P106、L1-2)と考えるし、巫臣がその「風」の吉凶を「凶」と言うことで、巫臣の夏姫を得る謀略の端緒となるのである。
この「風」は、創作上の春秋時代の人々をよりリアルに描くために作者が導入した観念、レトリックであるともいえるし、「なぜ、夏姫を撫有した者はつぎつぎに奇禍に遭い、巫臣だけがその災厄からまぬかれたのか」の問いの作者なりの答えでもある。つまり、「夏姫には、風伯が宿っているらしい」という観念は、春秋時代の人々のものとしてはそれらしく現実的なものであろう設定として小説世界に持ち込まれている。それと同時に、宮城谷の歴史解釈として、史実の夏姫にまとわりつく「風」が、史実上の男たちを破滅させ、「風」の正体を知りえた巫臣だけが「災厄からまぬかれた」と考えるわけである。これは別に小説の創作と歴史解釈とを混同させているわけではない。実際、創作上の「風」と史実上の「風」は、矛盾しない併存が可能なのである。
「英雄とは、風だ」(上P128、L7)という表現が、ひとつ作中に現われている。ここの「英雄」は、むろん夏姫のことではない。夏姫の父である鄭の穆公が、晋の文公に感じ、楚の荘王に感じる風である。この「英雄」が「動けば、あたりはさわさわと音を発し、空気に流れが生ずる」(上P128、L8)。この「風」は、言い換えれば、歴史の脈動、流れのようなものである。そして実は、夏姫にまとわりつく「風」もこれと同じものである。だが、この「風」がひとたび暴風となり、「凶風」となれば、人間さえ吹き飛ばし、破滅させてしまう。夏姫を撫有した者の奇禍は、この「凶風」であり、歴史の脈動、流れのひとつの顕れである。
この「風」の「凶風」としての姿は、中島「妖氛録」の「妖氛」と同じものである。Ⅰ節で、この「妖氛」を歴史の無常、不条理と言い換えたが、「凶風」も同じように言い換えてよい。宮城谷の夏姫にとっての歴史の不条理とは、「すべてが、やむをえなかった」(下P73、L5)という行動をとるうちに、周囲の人間たちが次々と不幸になっていくことである。
だが、この歴史の無常、不条理に対する態度の違いは、中島と宮城谷の間で明白である。不条理小説としての「妖氛録」には、「妖氛」に対する一種の諦観しかなく、その中で人間たちは一切救済されず、彼らには笑うしか選択が残されていない。だが、『夏姫春秋』では、歴史の「凶風」から人間を、まず夏姫という一人間を救おうとする。この夏姫を歴史の泥寧から救いあげる作業は、作者宮城谷と作中の巫臣との共同作業である。二人は「夏姫を幸せにできる男は、この世で自分しかいない」との想いを共有して、この作品を作りあげている。また、作中の夏姫も自分を救いあげるべく、必死の手を伸ばす。これは人間を歴史より優位におこうとする闘いであり、宮城谷の夏姫はこの闘いに勝利をおさめる。かくして夏姫は、巫臣と結ばれることで歴史の「凶風」から解放されるのである。
ここに至っては、この作品で夏姫の「悪」が問題にならないことが理解できよう。夏姫の周囲の男たちの破滅は、「風」の所為、歴史の所為である。彼らの主体性を尊重し、それも救いあげるとするなら、彼ら自身の責任である。夏姫の動機からも責任からも「悪」と断じうる要素はまずない。夏姫自身は、「かの女の精神は無邪気である」(上P170、L12)、「夏姫は童女だ」の言葉が示す通りの無垢さである。「悪」は、「神の大いなる悪意」(上P242、L17)の結果であって、夏姫のものではない。「夏姫への愛」を抱く作者は、夏姫の「悪女」性を徹底的に否定している。
問題となるのは、夏姫の主体性である。宮城谷の夏姫は、海音寺の夏姫などよりは余程行動的である。しかし、「悪女」夏姫をこの上なく強調した駒田の夏姫と比べると、やはり巫臣と結ばれる前後の夏姫は弱い存在となっている。夏姫救済のテーマから言っても、歴史の「凶風」に縛られ、主体的行動が限定され抑圧されているのは「やむをえなかった」のかも知れない。必死でもがき、手を伸ばした先が男性(巫臣)であるというのも、歴史的女性像の限界性をリアルに描きだしていると言うこともできるかも知れない。だが、男性作家が描く女性像であるがゆえに、男性に救われる女性像を恣意的にか無意識的にか描き出したとして、作家の限界を指摘することもできる。この点は、女性による批評なり、新たな労作なりが待たれるが、そうした点を消捨すると、中島、海音寺の夏姫はまず問題外として、駒田の夏姫よりもさらに生き生きと息づく夏姫の主体が見えてくる。宮城谷の夏姫は、駒田の夏姫にない葛藤をし、自身の限界を越えられないために、自分と他者の不幸に悩む。そして、巫臣の差し出す手を取ることを選んだのは、夏姫自身の選択である。これもやはり夏姫にとって「やむをえない」選択であって、夏姫は何ら救済されていないという見解は成り立ちうる。また、「救済」という用語自体がけしからんという議論もできるが、ここではそこまで論及しないでおこう。
[夏姫をいかに評価すべきか]
工事中!
夏姫夜話にもどる
枕流亭ホームにもどる