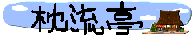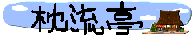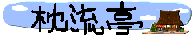
『天竺熱風録』を読み解く
田中芳樹『天竺熱風録』(新潮社)を中国史料をもとに読み解いてみようというだけの頁です。
最初にいくつかお断りですが、本作を読むつもりがあってまだ読んでないかたは、できればご遠慮ください。また小説のイメージを壊されたくないというかたも、引き返されることをお勧めします。
それから筆者は田中ファンでもあるし、中国史好きでもありますが、仏教には詳しくないし、チベット史にもネパール史にもインド史にも知見がありませんので、おかしなことを書いてる場合もあろうかと思います。情報提供お願いします。(注文の多い料理店で申し訳ないです。)
コラムページのトップへもどる
ホームへもどる
「熱き志、冴える知謀。インド誇る戦象軍団を撃破した男。その名は、王玄策。」
ハードカバーの帯についたキャッチコピー(新潮社の人間が考えたんだろうけど)ですが、長年田中ファンをやってきた人間には、こみあげるものがありますね。よくも待たせてくれたなという積年のうらみと、大仰なコピーに見え隠れする滑稽さと。帯というのは面白いものです。「中国史最強の外交官」ってのもなんでしょうかね。
『天竺熱風録』は王玄策らによる遣天竺使節をテーマにした小説ですが、王玄策について歴史上で分かっていることは非常に少ない。もととなる史料がおどろくほど少ないのです。それで歴史小説としても、作家の創意にかかる部分が大きくなっています。
▼彼岸法師と智岸法師と王玄廓
今回の物語の狂言回しをつとめたのは、ふたりの坊さん、彼岸法師と智岸法師でした。とくに彼岸法師の性格の良さに笑った人は少なくなかったと思います。まずこのふたりから攻めてみます。
彼岸法師と智岸法師については、王玄策以上に史料が残っていません。分かっていることは、ともにトルファン(高昌、現新疆自治区吐魯番)出身であること、長安で勉強したこと、海路をとって求法の旅に出たこと、王玄廓と同船したこと、海上で病にあってともに亡くなったこと、たずさえた漢本の瑜伽ほかの経典が室利仏逝国(シュリーヴィジャヤ、今のインドネシア)にあったこと、くらいしか分かりません。伝が義浄『大唐西域求法高僧伝』にありますが、しごく短いです。
小説と比べるほどのものでもありませんが、ふたりが三蔵法師玄奘の弟子だったという記述はありません。王玄策と行をともにしたという記録はありません。彼岸法師があのような問題性格だったという記述もありません。そもそもインドに到達してすらいません。小説のとおりなのは、ふたりが高昌出身で、長安で勉強して、海上で病にあって亡くなったことくらいです。短いながらも彼らの伝記が残っているのは、経典をシュリーヴィジャヤに伝えた功績があったからです。しかもその経典はインドのものではなく、漢訳された経典だったりします。
王玄廓については、さらにあきれることに、使者であったことと、ふたりの坊さんと海路で同行したことしか分かっていません。小説では王玄策の従弟と設定されていますが、姓と諱の一字が共通という以外の根拠はありません。ただ記録にないだけで、王玄策の親族であった可能性は完全に否定できるものではないでしょうけども。
※馮承鈞『王玄策事輯』では、王玄廓は王玄策の誤りで、彼岸法師と智岸法師が王玄策に同行したという説を採っているようです。王玄策は一度も海路を取っていないので、きわめて疑わしく思えますが。孫修身『王玄策事跡鈎沉』では、馮説を否定して、王玄廓は王玄策の兄弟か洛陽王氏の同輩の可能性を示唆しています。
▼王玄策の天竺行第一回
王玄策の第一回遣天竺使節の事情については、小説の微妙な省略があります。当時の北インドを制覇した戒日王ハルシャ・ヴァルダナ(中国史書では尸羅逸多)は、玄奘三蔵を通じて唐の太宗(李世民)の英雄ぶりを知っていました。玄奘と会う以前から「秦王破陣楽」(ありし日の秦王李世民が劉武周の陣を破る英雄ぶりを讃えた雅楽のこと)を聞き知っていたともいいます。貞観十五年(641)、戒日王は唐と好を通じようと太宗のもとに使者を送ってきます。太宗の命を受けて梁懷璥がこの使者の応対接遇にあたり、太宗の詔が戒日王に下されます。戒日王の使者の帰国に合わせて、この太宗の詔書をもった使者が派遣されているはずですが、詳細は不明です。戒日王は「いにしえより摩訶震旦(作中のマハー・チーナと同じ、中国を指す)の使者が我が国にいたったことがあるだろうか」と驚いて、再び唐に使者を送ってきます。この使者を応接したのが李義表でした。返礼として、太宗は李義表を正使とする使者を送ります。李義表はこのとき朝散大夫・衛尉寺丞・上護軍の地位にありました。副使の王玄策は、前職が融州黄水県令(任地は現広西融水苗族自治県、つまり桂林の西の県知事、従七品下)だったといいます。派遣された人数は合わせて二十二人でした(二十二人の中に魏才とか宋法智とかいう人がいたらしい)。小説の説明(P22~P24)は、唐・天竺間の使者の往来が一往復分抜け落ちているのですが、まああまり深く追求しないことにします。
この李義表の遣天竺使節は、途中で泥婆羅国(ネパール)に立ち寄って、その王の那陵提婆と面会しています。このとき那陵提婆は大喜びで、阿耆婆沵池なるものを見せたといいます。こんこんと湧き出る水、立ち上がる煙、釜をかけると炊飯することができたそうで、火山性の温泉のようなものでしょう。このくだりを小説は無視していますが、あまり面白くない挿話だからでしょうか?
『法苑珠林』によると、李義表の使節は貞観十七年(643)十二月にインドに到着します。仏教遺跡を遊覧してまわったようです。十九年(645)正月二十七日に、王舍城に到着。耆闍崛山に登ってみたりと、ずいぶんとのんびり観光してるように思えます。
▼天竺行第二回へ出発
李義表の使節を受けて、戒日王ハルシャ・ヴァルダナはまた唐に使者を送って、火珠・鬱金・菩提樹を太宗に献じました。
ここから貞観二十一年(647)、本作のメインテーマである王玄策の天竺行第二回につながります。正使は王玄策、副使は蒋師仁です。以下の随員は不詳です。小説での彼岸・智岸・王玄廓の位置づけが、実際ではどうだったかは前述したので繰り返しません。
このときの王玄策は右衛率府長史。正七品上の位であることは間違いないようですが、この位は皇太子の護衛官であって、小説(P24)で「皇城を警備する一部隊の副隊長」とか言っているのは、不正確です(東宮官であることに言及していない上に、率と副率の次の位ですから副隊長ではありません)。
▼吐蕃
小説の第二回三節のくだり(P54~P57)で、王玄策は吐蕃に立ち寄ります。吐蕃は現在のチベットにあった独立国です。
このころの吐蕃は、はじめてチベットを統一したソンツェンガンポ王の時代ですが、両唐書の吐蕃伝のほかは、伝承のようなものが多く、事実の確定が難しいことが多いようですね。
小説もやっかいなところとみて、あっさり簡単に片づけてる感じがします。
下のページなどは、参考として面白いかもしれません。
http://zhuling.cool.ne.jp/xiangbala/wcgz/pingjia.htm
ネパール王女ブリクティ(ティツィン)は、ナレーンドラデーヴァの娘の可能性が高い…ですか。
さておきインドで起こる事件について吐蕃が王玄策に協力した理由には、唐と吐蕃の同盟関係と、文成公主の存在が大きいと思われるのですが、小説では軽く流されてますね。
▼泥婆羅
小説の第二回四節のくだり(P59~P61)で、王玄策はネパールに立ち寄ります。中国史書では、このころのネパールを泥婆羅国と書いています。ここでの話も基本的にはつくりです。
ここで少し田中氏の年季の入った勘違いを指摘しなければなりません。
小説では「ネパール国主の名はアムシュヴァルマン」と述べられているのですが、アムシュヴァルマン(Amsuvarman)の在位年は西暦605年から621年までであり、このときにはすでに亡くなっています。
このときのネパール国主はナレーンドラデーヴァ(Narendradeva、在位年643-679)です。両唐書でも那陵提婆と書かれています。
ネパールのリッチャヴィ朝の諸王については
http://en.wikipedia.org/wiki/Licchavi
ほかで参照できます。
田中氏のネパール王名の勘違いは、「私撰中国歴代名将百人」(『小説中公』1995年3月号初出,『談論中国名将の条件』、『中国武将列伝』所収)のころからカマしているものなので、長年のものなんでしょう。
▼王玄策、入国をはばまれる
王玄策がインドに入ろうとしたころ、ときに戒日王は亡くなっており、ティラブクティ王アルジュナ(『資治通鑑』では帝那伏帝王阿羅那順、両唐書では那伏帝阿羅那順)が王位を簒奪していました。アルジュナは兵を発して王玄策をはばみます。王玄策は三十騎を従えて戦い、衆寡敵せず、矢が尽きてことごとく捕らえられ、諸国の貢物を奪われてしまいます。小説ではこのとき戦いらしい戦いをしていないのですが、両唐書ではしっかり戦っているようです。王玄策の従えた騎兵は、『旧唐書』や『資治通鑑』では「悉被擒」(ことごとく捕らわる)と書かれているのですが、『新唐書』では「皆沒」(みな没す)とあり、後者を取ると全員亡くなったようにも読めます。
※梵文『龍喜記』によると、「(アルジュナは)中国の使者を攻撃し、財物を奪い、その随従を殺した。王玄策は余の少数の随従とともに夜間脱出した」ということです。
▼吐蕃から千二百人、泥婆羅から七千余騎を借りる
アルジュナのもとからの王玄策の脱出劇は、宵のうちだったということ以外、詳細は不明です。小説の展開はまたしても創作と言っていいでしょう。
王玄策は吐蕃の西辺に逃れ、檄(触れ文)を発して隣国の兵を召集します。吐蕃が兵千二百人をよこし、泥婆羅が七千騎をつかわしてきました。小説で王玄策がネパールに援軍を求めるくだりも創作です。
※梵文『龍喜記』によると、王玄策は泥婆羅に逃れたことになっています。それ以外の史料(両唐書や通鑑など)では、すべて吐蕃に逃れたことになっています。
▼茶鎛和羅城で戦う
貞観二十二年(648)五月、王玄策は二カ国の兵を率いて、茶鎛和羅城に進軍し、三日してアルジュナの軍を破り、斬首三千級、溺死一万余という勝利を挙げます。小説では赫羅赫達の戦いと茶鎛和羅の戦いに分けられていますが、一連の戦闘描写はこれまた創作です。中国史書では、象さん軍団の姿はまるで見えません。ちなみに史書では茶鎛和羅城は中天竺の都城あつかいされています。茶鎛和羅イコール曲女城(カナウジ)と考えるべきでしょう。
アルジュナは敗走して、残兵を収容再編し、再び陣立てしますが、蒋師仁に敗れて捕らえられてしまいます。蒋師仁はこのとき捕虜千人あまりを斬ったとあります。
※赫羅赫達の地名は梵文『龍喜記』に出てきます。
▼アルジュナの妻子
天竺側の残兵はアルジュナの妻子を立てて、乾陀衛江を防衛線にして王玄策の軍をはばみますが、蒋師仁に敗れてアルジュナの妻子は捕らえられます。このあたり史書では副使の蒋師仁のほうが名将(笑)のようにも見えます。小説ではアルジュナの妻が曲女城に立て籠もって、内から開城される展開ですが、これも史書と異なります。
アルジュナの妻が小説のような猛女であったとか、アルジュナの子が小説のようによくできた子であるような記述は史書には見られません。
▼王玄策の戦果
両唐書によると、王玄策と蒋師仁らは、天竺の男女一万二千人を捕虜とし、雑畜三万頭をとらえ、城邑五百八十カ所を降しました。東天竺王尸鳩摩は牛馬三万と軍、そして弓、刀、宝桜絡を送ってよこしました。迦没路国の童子王は珍奇な物(?)と地図を献上し、代わりに老子像と『道徳経』を求めました。
王玄策の帰国は貞観二十二年(648)十月ごろと推測されています。王玄策は帰国すると、捕らえたアルジュナ(阿羅那順)を太宗に献上しました。太宗は「アルジュナが夫人の耳目を声色で楽しませ、口鼻を香りや味にふけらせたのが、このたびの敗徳の原因である。婆羅門(アルジュナ)がわが使者(王玄策)を抑留しなければ、かえって捕虜になるようなことがあったろうか?」といいました。王玄策は功績により朝散大夫に抜擢されました。これは従五品下の官位です。のちに太宗が昭陵に葬られると、アルジュナの形の石像が刻まれて、地下の宮殿にならべられたともいいます。
ちなみにアルジュナ捕縛後のインドの状況ですが、混乱をきわめたというのが実際のようです。小説で新王の役回りを当てられている地婆西那という人物は、『旧唐書』に出てきます。天授二年(692)、中天竺王地婆西那など五天竺王が唐に朝献した記事が見えます。この人物がアルジュナ捕縛後すぐに即位した人物だという根拠はありません。王玄策はべつだんインドに秩序をもたらしたわけではないのです。
▼バラモン那羅延娑婆寐
作中には、彼岸・智岸のほかもうひとりの狂言回しがいます。老バラモン那羅延娑婆寐(ナーラーヤナスヴァーミン)です。王玄策が方士那羅邇娑婆寐を連れ帰ったことは史書にあります。齢二百歳と自称していたのもそのとおりです。長生の術を会得していると吹聴していたのも本当です。晩年の太宗はかれを崇敬し、かれの煎じた奇薬を呑みましたが、当然ながら効かなかったとあります。のちには太宗が死んだのは、かれのせいということにされています(笑)。
小説第十回三節(P286~P288)に、李勣が那羅延娑婆寐の老いた姿を喝破して、長生不老に興味を示す太宗を諫めるシーンがありますが、これは実はずっと後の顕慶二年(657)に、高宗(李治)と李勣の間に交わされた会話を改変したものです。
那羅邇娑婆寐は高宗のころに長安で亡くなっています。
▼精糖法について
小説中であまり注目されないかもしれませんが、太宗が精糖法をインドに求めたという話は『新唐書』に見えます。太宗が摩伽陀国(マガダ国)に遣使して「熬糖法」を取り、そこで詔を下して揚州からさまざまなサトウキビを上納させ、伝来どおりにやってみましたが、色味ともに西域のものに遠く及ばなかったといいます。
また『続高僧伝』によると、専門の匠二人と僧八人が唐にやってきています。勅命により越州でサトウキビを作らせたところ、成功したといいます。
▼仏足石について
日本の奈良薬師寺の仏足石銘文によると、王玄策の第二回遣天竺使節のとき、鹿野園の仏足石をみて転写し、これを中国に持ち帰ったんだそうです。
日本には、転写の転写が天平勝宝年間に伝わっているようです。
▼道王の友
天竺行第二回と第三回の間の八年間くらい、王玄策が何をやっていたかよく分かりません。『唐文続拾』の貞観二十三年(649)十二月の条に「和籴副使、左監門長史王玄策」とあります。和籴副使は穀物の買い入れを担当する官です。左監門長史は従六品上の官位です。
また、道王(李元慶)の友として任官してたという話が『資治通鑑』にあります。李元慶は唐の高祖(李淵)の子のひとりです。友は諸王府に陪侍するもので、従五品下の官位です。出世してません。那羅邇娑婆寐が懲りずに高宗に長生薬を献上するのにつきあってます。
▼天竺行第三回
『法苑珠林』によると、王玄策は顕慶二年(657)に敕使として西国におもむいています。理由は仏袈裟を送るためとなっています。このときの官位は右驍衛率府長史(従六品上)です。翌年、泥婆羅国(ネパール)西南に立ち寄って水火池というものを鑑賞しているようです。
顕慶四年(659)に婆栗闍国(ヴリジ)にいたり、国王に盛大な宴の歓迎を受け、女戯(女性の雑技)を鑑賞しているといいます。色ボケ王玄策説も根拠なしとはいえないかもしれません(笑)。
顕慶五年(660)に摩訶菩提寺に石碑を建てています。またこの年に罽賓国・烏萇国といった国々に立ち寄ってるようです。
王玄策の帰国は、龍朔元年(661)春のようです。
『大唐西域求法高僧伝』によると、帰国後高宗に奏上して、太州出身の玄照法師を帰国させるよう働きかけています。この書の玄照法師の伝より四度目の遣使(663年-665年)があったのだという説もあるようです。
『全唐文』の「議沙門不応拜俗状」によると、王玄策は龍朔年間(661年-663年)に左驍衛長史(従六品上)に進んでいます。
麟徳二年(665)、王玄策が洛陽敬愛寺の塑像建立を指揮したり、龍門石窟で弥勒像を造ったりという話しもあるようです。
▼智弘律師
『大唐西域求法高僧伝』によると、智弘律師という人がいて、この人は王玄策の甥にあたります。この人の本籍について洛陽の人と記述されているので、王玄策の本籍も洛陽ということにされているようです。この智弘律師も海路を取ってインドに入っているというのは、血は争えない?のでしょうか。
▼象兵と戦った人たち
小説(P180)に「古来、南方に遠征して象軍と戦い、武勲をかがやかせた将帥といえば、後漢の馬援、南朝の檀和之、隋の劉方でございます」とあります。中国兵vs象軍団の真実やいかに?ということで、ここも追求してみます。
馬援(前14~49)は、後漢の将軍です。建武十七年(41)から十九年(43)にかけて、伏波将軍となって交趾の徴側・徴弐姉妹の乱を鎮圧しています。しかし象兵と戦ったという話は見えません。馬援は中国史でもけっこう有名な人で、「井の中の蛙」や「矍鑠たるかなこの翁」の挿話で知られています。
檀和之(?~456)は、南朝宋の将軍で、元嘉二十三年(446)に文帝の命を受けて林邑(ヴェトナム南部)を攻めています。たしかに林邑王范陽邁は鎧をつけた象軍団を率いていたようです。振武将軍の宗慤(?~465)が「外国では獅子が百獣を威服させる」といって獅子の形代で象を防がせると、象は驚き混乱して林邑軍は敗れたとかいう嘘くさい話が伝わっています。檀和之は何をしたかというと、先だって区粟城を囲んでいたのですが、林邑の将軍范毗沙達の援軍をはばむために軍を割いて敗れています。その尻拭いをして范毗沙達を破り、区粟城を落としたのはやはり宗慤です。(『南史』巻37宗慤伝による。『資治通鑑』では檀和之の格好悪いところがカットしてあるので、檀和之が区粟城を落としたように読めます。部下の手柄は上司の功績みたいな感じでしょうか?)「武勲をかがやかせた将帥」というにはかなり躊躇を覚えます。檀和之はその後の人生も格好悪く、文帝を殺した劉劭についたり、のちに劉駿に帰順したものの投獄されてむすめを入内させることで許されたり、なにやら面白そうな人ではありますけど。
劉方(?~605)は、北周から隋にかけての将軍です。大業元年(605)に、林邑王梵志を攻めたときに、象兵と出会っています。象を落とし穴に引き込み、弩を射て混乱させて勝ったようです。結果、林邑国都を落としますが、凱旋途中で病没してしまいます。この人の軍令は厳粛で、違反したものは斬ったといいます。また士卒をいたわり、病にあった者は親しく面倒をみたため、士卒もかれになついたといいます。なにやら呉起みたいな話です。劉方は『中国武将列伝』でも取りあげられていますが、もしかしたら名将かも、という程度の人です。伝わっている戦歴も挿話も少なすぎます。
▼余談-違和感の小説
思うに『天竺熱風録』を一言で表せば、「違和感の小説」ということになるでしょう。
まず最初に感じるのは、作者自身が「擬講釈文」と呼ぶあの文体への違和感です。慣れればさほどではなく、読みやすくもあるのですが。氏の小説に親しんでいるものとしては驚きでした。
また作中で四カ国にまたがる話でありながら、文化的な差異やエキゾチズムを表現するには、未消化な部分が多く、平板に世界がつながっているかのような違和感を感じました。しかしここは作者が後記で「比較文明論ではない」と言っているのを言い分として聞いておきます。
「単なる娯楽小説」という作者の言を信用してみましょう。
一読したときに違和感を覚えたのは、彼岸法師と智岸法師がなぜ取ってつけたように死ななくてはならなかったのか?ということです(『アルスラーン戦記』でイリーナ内親王が亡くなっていたことが唐突に明かされたときのようなショックでした。あれはあれでヒルメス出馬のために必要ではありましたが…)。悲劇調の作品ならそれもよいでしょう。しかし作品の調子は基本的に明るいのです。明るい娯楽小説なら、彼らがあのようなかたちで死ななければならない必然性はありません。もちろん歴史として見たときには、彼岸法師と智岸法師は海の上で病にかかって死んでいるという結論が投げ出されています。だから歴史小説として、彼らは死ななければならなかったのでしょうか。ならばなぜ歴史を曲げて彼らを王玄策に同行させ、インドに到達させたのでしょうか。娯楽小説としても歴史小説としても、半端なところを感じます(それでいながら読後しばらくして納得できるような気もするのですけども…やはりかれらは必要だったかと)。
牛を使ったトリックが二回出てくるように、やはり取ってつけたような危機脱出手段、デウス・エクス・マキナもどうかと思います。「寡をもって衆を撃つ」が成功するのは戦争の例外であるし、具体的な戦闘描写をともなう史料が残っていない以上、作家がトリックを考えなければならないつらさはあるにしても。しかし優れた術策を考えるのは、娯楽作家の責務であり、やはり腑に落ちないところを覚えます。
娯楽小説としては完全な構築を放棄したまま投げ出されたというもやもやした読後感が残ります。もしかして王玄策をはじめて紹介した小説として、後々に宿題を押しつけたのかもしれません。
歴史小説としてみた場合は、やはり歴史としての見方が入ります。あの事件での吐蕃と文成公主の働きを軽視している作者の見方には個人的に賛成できない…ことはとりあえず脇に置いておきまして。アルジュナを完全な悪玉にはしていないものの、王玄策を真っ当な報復者として提示し、アルジュナ打倒を正当化している無邪気さには首をひねりました。(いま中東あたりが騒がしいから、こんな書きかたすると誤解されますよ)簒奪イコール悪ではないことを『銀河英雄伝説』で強調している氏のことなんですから、もう少し立ち位置を考えてほしかった。
いろいろ言いましたが、違和感を呑みこみつつ、個人的には楽しませていただきました。田中氏のえらいところは、出版社も自分もさして潤わないのに、こういう知られざるテーマを発掘して書いてくださることです。氏にしてはめずらしく、精糖法や仏足石といった文化的なことにも言及していましたし。
最後に王玄策関係の論文は、こんなにあるらしいです。史実を追求するというのもたいへんです。
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~takata/wang_bibl.html
ちなみに拙文は、論文などはほとんど参照せずに書いてますから、田中氏の小説以上に信用ならない代物としてご承知おきください。逐一断ってはいませんが、ネット上のテキストは色々と参照させていただきました。ありがとうございました。
▼資料
『旧唐書』本紀第三太宗下貞観二十二年
五月庚子,右衛率長史王玄策撃帝那伏帝國,大破之,獲其王阿羅那順及王妃、子等,虜男女萬二千人、牛馬二萬餘以詣闕。使方士那羅邇娑婆於金飆門造延年之藥。吐蕃贊普撃破中天竺國,遣使獻捷。
『旧唐書』列伝一百四十六吐蕃上
二十二年,右衛率府長史王玄策使往西域,為中天竺所掠,吐蕃發精兵與玄策撃天竺,大破之,遣使來獻捷。
『旧唐書』列伝一百四十八西戎
貞觀中,衛尉丞李義表往使天竺,塗經其國,那陵提婆見之大喜,與義表同出觀阿耆婆源沵池。周迴二十餘歩,水恆沸,雖流潦暴集,爍石焦金,未嘗增減。以物投之,即生煙焰,懸釜而炊,須臾而熟。其後王玄策為天竺所掠,泥婆羅發騎與吐蕃共破天竺有功。永徽二年,其王尸利那連陀羅又遣使朝貢。
『旧唐書』列伝一百四十八西戎
貞觀十年,沙門玄奘至其國,將梵本經論六百餘部而歸。先是遣右率府長史王玄策使天竺,其四天竺國王咸遣使朝貢。會中天竺王尸羅逸多死,國中大亂,其臣那伏帝阿羅那順簒立,乃盡發胡兵以拒玄策。玄策從騎三十人與胡禦戰,不敵,矢盡,悉被擒。胡並掠諸國貢獻之物。玄策乃挺身宵遁,走至吐蕃,發精鋭一千二百人,倶泥婆羅國七千餘騎,以從玄策。玄策與副使蒋師仁率二國兵進至中天竺國城,連戰三日,大破之,斬首三千餘級,赴水溺死者且萬人,阿羅那順棄城而遁,師仁進擒獲之。虜男女萬二千人,牛馬三萬餘頭匹。於是天竺震懼,俘阿羅那順以歸。二十二年至京師,太宗大悅,命有司告宗廟,而謂群臣曰:「夫人耳目玩於聲色,口鼻耽於臭味,此乃敗德之源。若婆羅門不劫掠我使人,豈為俘虜耶?昔中山以貪寶取弊,蜀侯以金牛致滅,莫不由之。」拜玄策朝散大夫。是時就其國得方士那羅邇娑婆寐,自言壽二百歳,云有長生之術。太宗深加禮敬,館之於金飆門内,造延年之藥。令兵部尚書崔敦禮監主之,發使天下,採諸奇藥異石,不可稱數。延歴歳月,藥成,服竟不效,後放還本國。太宗之葬昭陵也,刻石像阿羅那順之形,列於玄闕之下。
五天竺所屬之國數十,風俗物産略同。有伽沒路國,其俗開東門以向日。王玄策至,其王發使貢以奇珍異物及地圖,因請老子像及道德經。那掲陀國,有醯羅城,中有重閣,藏佛頂骨及錫杖。貞觀二十年,遣使貢方物。天授二年,東天竺王摩羅枝摩、西天竺王尸羅逸多、南天竺王遮婁其拔羅婆、北天竺王婁其那那、中天竺王地婆西那,並來朝獻。景龍四年,南天竺國復遣使來朝。景雲元年,復遣使貢方物。開元二年,西天竺復遣使貢方物。八年,南天竺國遣使獻五色能言鸚鵡。其年,南天竺國王尸利那羅僧伽請以戰象及兵馬討大食及吐蕃等,仍求有及名其軍,玄宗甚嘉之,名軍為懷德軍。九月,南天竺王尸利那羅僧伽寶多枝摩為國造寺,上表乞寺額,敕以歸化為名賜之。十一月,遣使冊利那羅伽寶多為南天竺國王,遣使來朝。十七年六月,北天竺國三藏沙門僧密多獻質汗等藥。十九年十月,中天竺國王伊沙伏摩遣其大德僧來朝貢。二十九年三月,中天竺王子李承恩來朝,授游撃將軍,放還。天寶中,累遣使來。
『新唐書』列伝一百四十一吐蕃上
二十二年,右衛率府長史王玄策使西域,為中天竺所鈔,弄贊發精兵從玄策討破之,來獻俘。
『新唐書』列伝一百四十六西域上
初,王那陵提婆之父為其叔所殺,提婆出奔,吐蕃納之,遂臣吐蕃。貞觀中,遣使者李義表到天竺,道其國,提婆大喜,延使者同觀阿耆婆沵池。池廣數十丈,水常湓沸,共傳旱潦未始耗溢,或抵以物則生煙,釜其上,少選可熟。二十一年,遣使入獻波稜、酢菜、渾提葱。永徽時,其王尸利那連陀羅又遣使入貢。
『新唐書』列伝一百四十六西域上
武德中,國大亂,王尸羅逸多勒兵戰無前,象不弛鞍,士不釋甲,因討四天竺,皆北面臣之。會唐浮屠玄奘至其國,尸羅逸多召見曰:「而國有聖人出,作秦王跛陣樂,試為我言其為人。」玄奘粗言太宗神武,平禍亂,四夷賓服状,王喜,曰:「我當東面朝之。」貞觀十五年,自稱摩伽陀王,遣使者上書,帝命雲騎尉梁懷璥持節尉撫,尸羅逸多驚問國人:「自古亦有摩訶震旦使者至吾國乎?」皆曰:「無有。」戎言中國為摩訶震旦。乃出迎,膜拜受詔書,戴之頂,復遣使者隨入朝。詔衛尉丞李義表報之,大臣郊迎,傾都邑縱觀,道上焚香,尸羅逸多率群臣東面受詔書,復獻火珠、鬱金、菩提樹。
『新唐書』列伝一百四十六西域上
二十二年,遣右衛率府長史王玄策使其國,以蒋師仁為副;未至,尸羅逸多死,國人亂,其臣那伏帝阿羅那順自立,發兵拒玄策。時從騎纔數十,戰不勝,皆沒,遂剽諸國貢物。玄策挺身奔吐蕃西鄙,檄召鄰國兵。吐蕃以兵千人來,泥婆羅以七千騎來,玄策部分進戰茶鎛和羅城,三日破之,斬首三千級,溺水死萬人。阿羅那順委國走,合散兵復陣,師仁禽之,俘斬千計。餘衆奉王妻息阻乾陀衛江,師仁撃之,大潰,獲其妃、王子,虜男女萬二千人,雜畜三萬,降城邑五百八十所。東天竺王尸鳩摩送牛馬三萬餽軍,及弓、刀、寶纓絡。迦沒路國獻異物,并上地圖,請老子象。玄策執阿羅那順獻闕下。有司告宗廟,帝曰:「夫人耳目玩聲色,口鼻耽臭味,此敗德之原也。婆羅門不劫吾使者,寧至俘虜邪?」擢玄策朝散大夫。
得方士那邏邇娑婆寐,自言壽二百歳,有不死術,帝改館使治丹,命兵部尚書崔敦禮護視。使者馳天下,采怪藥異石,又使者走婆羅門諸國。所謂畔茶法水者,出石臼中,有石象人守之,水有七種色,或熱或冷,能銷草木金鐵,人手入輒爛,以橐它髑髏轉注瓠中。有樹名咀賴羅,葉如梨,生窮山崖腹,前有巨虺守穴,不可到。欲取葉者,以方鏃矢射枝則落,為羣鳥銜去,則又射,乃得之。其詭譎類如此。後術不驗,有詔聽還,不能去,死長安。高宗時,盧伽逸多者,東天竺烏茶人,亦以術進,拜懷化大將軍。
『新唐書』列伝一百四十六西域上
摩掲它,一曰摩伽陀,本中天竺屬國。環五千里,土沃宜稼穡,有異稻巨粒,號供大人米。王居拘闍掲羅布羅城,或曰倶蘇摩補羅,曰波吒釐子城,北瀕殑伽河。貞觀二十一年,始遣使者自通于天子,獻波羅樹,樹類白楊。太宗遣使取熬糖法,即詔揚州上諸蔗,拃瀋如其劑,色味愈西域遠甚。高宗又遣王玄策至其國摩訶菩提祠立碑焉。後德宗自製鍾銘,賜那爛陀祠。
『資治通鑑』唐紀一五太宗貞観二十二年
五月,庚子,右衛率長史王玄策撃帝那伏帝王阿羅那順,大破之。
初,中天竺王尸羅逸多兵最強,四天竺皆臣之,玄策奉使至天竺,諸國皆遣使入貢。會尸羅逸多卒,國中大亂,其臣阿羅那順自立,發胡兵攻玄策,玄策帥從者三十人與戰,力不敵,悉爲所擒,阿羅那順盡掠諸國貢物。玄策脱身宵遁,抵吐蕃西境,以書徴鄰國兵,吐蕃遣精鋭千二百人、泥婆國遣七千餘騎赴之。玄策與其副蔣師仁帥二國之兵進至中天竺所居茶餺和羅城,連戰三日,大破之,斬首三千餘級,赴水溺死者且萬人。阿羅那順棄城走,更收餘衆,還與師仁戰;又破之,擒阿羅那順。餘衆奉其妃及王子,阻乾陀衞江,師仁進撃之,衆潰,獲其妃及王子,虜男女萬二千人。於是天竺響震,城邑聚落降者五百八十餘所,俘阿羅那順以歸。以玄策爲朝散大夫。
『資治通鑑』唐紀一六高宗顕慶二年
王玄策之破天竺也,得方士那羅邇娑婆寐以歸,自言有長生之術,太宗頗信之,深加禮敬,使合長生藥。發使四方求奇藥異石,又發使詣婆羅門諸國采藥。其言率皆迂誕無實,苟欲以延歳月,藥竟不就,乃放還。上即位,復詣長安,又遣歸。玄策時為道王友,辛亥,奏言:「此婆羅門實能合長年藥,自詭必成,今遣歸,可惜失之。」玄策退,上謂侍臣曰:「自古安有神仙!秦始皇、漢武帝求之,疲弊生民,卒無所成,果有不死之人,今皆安在!」勣對曰:「誠如聖言。此婆羅門今茲再來,容髮衰白,已改於前,何能長生!陛下遣之,内外皆喜。」娑婆寐竟死於長安。
『資治通鑑』唐紀十七高宗總章元年
冬,十月,戊午,以烏荼國婆羅門盧迦逸多為懷化大將軍。逸多自言能合不死藥,上將餌之。東臺侍郎郝處俊諫曰:「脩短有命,非藥可延。貞觀之末,先帝服那羅邇娑婆寐藥,竟無效;大漸之際,名醫不知所為,議者歸罪娑婆寐,將加顯戮,恐取笑戎狄而止。前鑒不遠,願陛下深察。」上乃止。
義淨『大唐西域求法高僧傳』巻上
太州玄照法師
後因唐使王玄策歸。表奏言其實。遂蒙降敕。重詣西天追玄照入京。路次泥波羅國。蒙王發遣送至吐蕃。重見文成公主。深致禮遇。資給歸唐。於是巡西蕃而至東夏。
義淨『大唐西域求法高僧傳』巻上
高昌彼岸智岸二人
彼岸法師。智岸法師。並是高昌人也。少長京師傳燈在念。既而歸心勝理。遂乃觀化中天。與使人王玄廓相隨汎舶。海中遇疾倶卒。所將漢本瑜伽及餘經論。咸在室利佛逝國矣。
義淨『大唐西域求法高僧傳』巻上
洛陽智弘律師
智弘律師者。洛陽人也。即聘西域大使王玄策之姪也。年纔弱歳早狎冲虚。志蔑輕肥情懷棲遁。遂往少林山餐和服餌。樂誦經典頗工文筆。既而悟朝市之諠譁。尚法門之澄寂。遂背八水而去三呉。捨素禔而擐緇服。事瑳禪師為師稟承思慧而未經多載即彷彿玄關。復往蘄州忍禪師處重修定歛。而芳根雖植崇條未聳。遂濟湘川跨衡嶺。入桂林而託想。遁幽泉以息心。頗經年載。仗寂禪師為依止。睹山水之秀麗。翫林薄之清虚。揮翰寫衷掣幽泉山。賦申遠遊之懷。既覽三呉之止。睹山水之秀麗。翫林薄之清虚。揮翰寫衷掣幽泉山。賦申遠遊之懷。既覽三呉之法匠。頗盡芳筵。歴九江之勝友。幾閑妙理。然而宿植善根匪由人獎。出日中府欲觀禮西天。幸遇無行禪師與之同契。至合浦升舶長泛滄溟。風便不通漂居上景。覆向交州住經一夏。既至冬末復往海濱神灣。隨舶南遊到室利佛逝國。自餘經歴具在行禪師傳内。到大覺寺住經二載。瞻仰尊容傾誠勵想。諷誦梵本月故日新。閑聲論能梵書。學律儀習對法。既解倶舍復善因明。於那爛陀寺則披覽大乘。在信者道場。乃專功小教。復就名德重洗律儀。懇懇懃懃無忘寸影。習德光律師所製律經。隨聽隨譯實有功夫。善護浮嚢無虧片檢。常坐不臥知足清廉。奉上謙下久而彌敬。至於王城鷲嶺僊苑鹿林祇樹天階菴園山穴。備申翹想東契幽心。毎掇衣缽之餘。常懷供益之念。於那爛陀寺則上餐普設在王舍城中乃器供常住。在中印度近有八年。後向北天羯濕彌羅。擬之郷國矣。聞與琳公為伴。不知今在何所。然而翻譯之功其人已就矣
『續高僧傳』巻四
又敕王玄策等二十餘人。隨往大夏。并贈綾帛千有餘段。王及僧等數各有差。并就菩提寺僧召石蜜匠。乃遣匠二人僧八人。到東夏。尋敕往越州。就甘蔗造之皆得成就。
『法苑珠林』巻第四
又王玄策西國行傳云。王使顯慶四年至婆栗闍國。王為漢人設五女戲其五女傳弄三刀加至十刀。又作繩伎。騰虚繩上著履而擲。手弄三仗刀楯槍等。種種關伎雜諸幻術。截舌抽腸等。不可具述。
『法苑珠林』巻第十六
唐顯慶二年。敕使王玄策等往西國。送佛袈裟。至泥婆羅國西南。至頗羅度來村東坎下。有一水火池。若將家火照之。其水上即有火焔於水中出。欲滅以水沃之。其焔轉熾。漢使等曾於中架一釜煮飯熟。使問彼國王。國王答使人云。曾經以杖刺著一金匱。令人挽出。一挽一深。相傳云。此是彌勒佛當來成道天冠金。火龍防守之。此池火乃是火龍火也。
『法苑珠林』巻第二十九
又依王玄策傳云。此漢使奉敕。往摩伽陀國摩訶菩提寺立碑。至貞觀十九年二月十一日。於菩提樹下塔西建立。使典司門令史魏才書昔漢魏君臨。窮兵用武。興師十萬。日費千金。猶尚北勒闐顏東封不耐。大唐牢籠六合道冠百王。文德所加溥天同附。是故身毒諸國道俗歸誠皇帝愍其忠款遐軫聖慮。乃命使人朝散大夫行衛尉寺丞上護軍李義表副使。前融州黄水縣令王玄策等二十二人巡撫其國。遂至摩訶菩提寺所菩提樹下金剛之座。賢劫千佛並於中成道。嚴飾相好具若真容。靈塔淨地巧窮天外。此乃曠代所未見。史籍所未詳皇帝遠振鴻風光華道樹。爰命使人屆斯瞻仰。此絶代之盛事。不朽之神功。如何寢默詠歌不傳金石者也。乃為銘曰:
大唐撫運,膺圖壽昌,化行六合,威稜八荒。身毒稽顙,道俗來王。爰發明使,瞻使道場。金剛之座,千佛代居。尊容相好,彌勒規模,靈塔壯麗,道樹扶疏。歴劫不朽,神力焉如。
『法苑珠林』巻第二十九
粤以大唐貞觀十七年三月内。爰發明詔。令使人朝散大夫行衛尉寺丞上護軍李義表副使前融州黄水縣令王玄策等送婆羅門客還國。其年十二月至摩伽陀國。因即巡省佛郷覽觀遺蹤。聖跡神化在處感徴。至十九年正月二十七日至王舍城。遂登耆闍崛山。流目縱觀。傍眺罔極。自佛滅度千有餘年。聖跡遺基儼然具在。一行一坐皆有塔記。自惟器識邊鄙。忽得躬睹靈跡。一悲一喜不能裁抑。因銘其山用傳不朽。
『法苑珠林』巻第五十五
即如大唐太宗文皇帝及今皇帝。命朝散大夫衛尉寺丞上護軍李義表副使前融州黄水縣令王玄策等二十二人。使至西域。前後三度。更使餘人。
『唐文續拾』巻十(貞観二十三年十二月の条)
和籴副使、左監門長史王玄策
『全唐文』巻二百四
元策貞観〔二〕十二年,右衛率府長史。使西域,為中天竺所鈔掠,元策發吐蕃兵破之,龍朔中,官左驍衛長史。
『奈良薬師寺仏足石銘文』
大唐使人王玄策,向中天竺鹿
野園中,轉法論處,因見
迹,得轉寫,塔(拓)是第一本。
日本使人黄文(書)本実,向
大唐国,于普光寺,得轉
寫,塔(拓)是第二本。此本在
右京四条一坊禅院,(以下略)。
コラムページのトップへもどる
ホームへもどる